介護保険の負担割合はどのくらい?所得ごとの計算方法から負担割合証の役割まで全て紹介
更新日時 2023/08/07
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
「介護保険の自己負担割合はどのくらい?」
「所得ごとの計算方法は?」
このように、介護保険の自己負担割合や利用条件、計算方法などがよくわからず、介護サービスをいつからどのように使えばよいのかと、悩んでいる人も多いでしょう。
介護保険サービスを上手に使うためには、介護保険の仕組み、特に自己負担の限度額を理解しておくことが大事です。
今回は、介護保険の負担割合について詳しく解説をしていきます。
また、サービス内容ごとの利用条件、所得ごとの計算方法、自己負担額の目途、負担割合証の役割などの関連する内容についてもご紹介します。
この記事を読めば、介護保険とその自己負担割合について、バッチリ理解することができるでしょう。
- 介護報酬は利用者の自己負担額と国の介護給付の合計になる
- 自己負担額は介護保険サービス料の1割が基本だが、収入・世帯構成次第で2・3割になる
- 要介護や要支援の介護度合いによって介護保険の支給限度額が異なる
介護保険の自己負担割合はどのくらい?
要介護認定を受けて介護保険サービスを利用した場合、介護事業者に介護報酬が払われます。
介護報酬は、利用者の「自己負担額」と国からの「介護給付」の合計です。最初に、介護保険の自己負担割合はどのくらいなのか、見ておきましょう。
自己負担割合は通常は1割
利用者の自己負担額は、自己負担割合で決まります。基本は介護保険サービス料の1割です。
ただし、この自己負担割合は、収入や世帯構成によって1~3割の間で変わります。また、毎年見直されるため、前年度と負担割合が異なる場合もあります。
収入の格差による負担の公平性を図るために導入されているもので、たとえば、65歳以上の方の1人世帯で、合計所得金額が160万円未満の場合、1割負担です。
サービス利用料金が1万円のときに支払う金額は、1000円です。残りは、介護保険料で1/2、国1/4・地方1/4の負担になります。
収入などの条件によって2割・3割の場合も
上記のように自己負担割合は、所得や世帯構成によっては、2割または3割になることもあります。
たとえば、現役並みの高所得がある高齢者の場合は、自己負担割合が2割または3割になることが一般的です。また、65歳以上の方が1人暮らしの場合と、65歳以上の夫婦世帯の場合でも異なります。
利用者や家族の収入、家族構成、その他の収入要素などが考慮され、最終的な自己負担割合が計算されます。
複雑に思うかもしれませんが、大切なことですので、計算方法をしっかり理解しておきましょう。
負担割合はいつからの収入で計算される?
負担割合は、前年度の収入によって計算がなされます。この際に、参照される収入は「合計所得金額」と呼ばれます。
合計所得金額は、前年の年金収入とその他の所得金額の合計から、各種控除や必要経費等を控除した金額です。
「その他の所得」とは、不動産所得、利子所得、年金を除く雑所得などです。つまり、合計所得金額から雑所得である年金所得を引いたものになります。
具体的な計算方法を以下のフローチャートにまとめておきますので参考にしてください。合計所得金額など値は、年末調整や確定申告を行なっていれば、市区町村でも確認できます。
65歳以上の人が世帯に1人の場合

まず、65歳以上の人が世帯に1人の場合について見ていきましょう。解説すると、以下のようになります。
- 本人の合計所得金額が160万円未満、または本人の年金収入とその他の合計所得が280万円未満なら1割負担
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で年金収入とその他の合計所得が280万以上、または本人の合計所得金額が220万円以上で年金収入とその他の合計所得が340万円未満なら、2割負担
- 本人の年金収入とその他の合計所得が340万円以上なら、3割負担
となります。
65歳以上の人が世帯に2人以上の場合

次に、65歳以上の人が世帯に2人の場合です。解説すると、以下のようになります。
- 本人の合計所得金額が160万円未満、または本人の合計所得金額が220万円未満で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が346万円未満なら1割負担
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が346万円以上、または本人の合計所得金額が220万円以上で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が463万円未満なら2割負担
- 本人の合計所得金額が220万円以上で本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が463万円以上なら3割負担
となります。
要介護・要支援段階それぞれに支給限度額がある
市区町村や地域包括支援センターなどに申請して要介護認定を受けると、居宅サービス・地域密着型サービスなど在宅で介護保険サービスを受けられます。その際、要介護・要支援の段階に応じた支給限度額があります。
要介護度とは、要支援1から要介護5まで7段階に分けられており、1が軽度の介護が必要な状態であり、5が重度の介護が必要な状態を示します。
この支給限度額を超えた利用分は、10割全額が自己負担になりますので、注意が必要です。
| 要介護度 | 支給限度額(円/月) |
|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 |
| 要支援2 | 105,310円 |
| 要介護1 | 167,650円 |
| 要介護2 | 197,050円 |
| 要介護3 | 270,480円 |
| 要介護4 | 309,380円 |
| 要介護5 | 362,170円 |
区分支給限度額は、サービスによっては含まれないものもあり、地域によって異なることもあります。
また、法改正によって変わることもありますので、利用の際には再度確認しましょう。
居宅(在宅)サービスの内容・自己負担割合
居宅(在宅)サービスの内容・自己負担割合について詳しく見ていきましょう。
在宅で介護を受ける場合は、介護保険の居宅サービスを使いますが、要支援・要介護認定を受けただけではサービスを利用することはできません。
要介護認定を受けた後に、ケアマネージャーにケアプランを作成してもらう必要があります。
受けられるサービスは、ケアプランに盛り込まれたサービスだけです。また、サービスの利用料は、区分支給限度額に含まれますので、超過しないように注意しましょう。
訪問介護
訪問介護は、利用者の自宅を訪問して介護サービスを提供するものです。自宅で普段通りの生活をしながら、介護福祉士や訪問介護員などによる、食事・排せつ・清拭・入浴などの身体介護を受けることができます。
また、健康管理や衛生面などの看護・アドバイスも行ってくれます。さらに、掃除・洗濯、買い物や調理などの生活支援サポートも存在します。
下の表は、訪問介護を利用したときの自己負担額の一覧です。
<身体介護が中心である場合>
| 利用する時間 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 20分未満の場合 | 167円 | 167単位 |
| 20分以上30分未満の場合 | 250円 | 250単位 |
| 30分以上1時間未満の場合 | 396円 | 396単位 |
| 1時間以上の場合 | 579円 | 579単位 ※30分を増すごとに+84単位 |
<生活援助が中心である場合>
| 利用する時間 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 20分以上45分未満の場合 | 183円 | 183単位 |
| 45分以上の場合 | 225円 | 225単位 |
<通院などのための乗車または降車の介助が中心である場合>
| 利用する時間 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| - | 99円 | 99単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
訪問介護のサービス内容は?身体介護・生活援助の内容や気になる料金まで解説!

訪問入浴介護
訪問入浴介護は、寝たきりなどのために自宅での入浴が困難な要介護者の家を訪問して、提供するサービスです。
通常、看護師1名・介護職員2名が、入浴専用車両に移動式浴槽と湯沸かし器を積んで訪問し、入浴を介助します。
訪問入浴介護の対象者は、要介護1以上の認定を受けた方です。入浴の前後に血圧や発熱の有無などをチェックします。
| 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 | |
|---|---|---|
| 入浴 | 1,256円 | 1,256単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
訪問看護
訪問看護は、自宅での療養生活をサポートするものです。医師の指示に基づき、看護師などが利用者の自宅を訪問して、健康チェックや傷の手当などの医療処置、床ずれ予防などのサービスを提供します。
主に、高齢者や病気で外出が困難な人で、継続的な医療ケアを必要とする方々に利用されます。
年齢や状態により、介護保険か医療保険のどちらかが適用されます。訪問看護は、介護者の負担を軽減できるメリットも大きいです。
<指定訪問看護ステーション>
| 利用する時間 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 20分未満の場合 | 313円 | 313単位 |
| 20分以上30分未満の場合 | 470円 | 470単位 |
| 30分以上1時間未満の場合 | 821円 | 821単位 |
| 1時間以上1時間30分未満の場合 | 1,125円 | 1,125単位 |
<病院または診療所による訪問看護>
| 利用する時間 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 20分未満の場合 | 265円 | 265単位 |
| 20分以上30分未満の場合 | 398円 | 398単位 |
| 30分以上1時間未満の場合 | 573円 | 573単位 |
| 1時間以上1時間30分未満の場合 | 579円 | 842単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
訪問看護のサービス内容は?料金や利用条件・訪問介護との違いまで全て解説

訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅に来てリハビリのサポートを行ってくれるサービスです。
利用できるのは要介護認定を受けているか、主治医が必要と診断した場合です。リハビリテーションの内容は、歩行や体操といった機能訓練や理学療法など、利用者の状況に合う最適なリハビリです。
訪問リハビリの利用頻度は、1回20分・週6回以内が限度になっています。利用する事業所は、利用者と家族が納得して決めましょう。
| 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|
| 307円 | 307単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
訪問リハビリテーションとは?対象者や費用・選ぶ際の注意点まで解説

通所介護(デイサービス)
通所介護は、いわゆるデイサービスです。
自宅からデイサービスセンターへの送迎を行ってくれます。施設には介護スタッフがおり、レクリエーションなどのイベントのほかに、食事や入浴といった生活支援・介護といった日帰りのサービスを受けることができます。
通所サービスの利用時間は、日中の3時間以上から9時間未満まで、いろいろなパターンから選ぶことが可能です。
利用料金・自己負担額は、利用時間に応じ高くなります。
通常規模型通所介護費
| 利用する時間 | 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 368円 | 368単位 |
| 要介護2 | 421円 | 421単位 | |
| 要介護3 | 477円 | 477単位 | |
| 要介護4 | 530円 | 530単位 | |
| 要介護5 | 585円 | 585単位 | |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 386円 | 386単位 |
| 要介護2 | 442円 | 442単位 | |
| 要介護3 | 500円 | 500単位 | |
| 要介護4 | 557円 | 557単位 | |
| 要介護5 | 614円 | 614単位 | |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 567円 | 567単位 |
| 要介護2 | 670円 | 670単位 | |
| 要介護3 | 773円 | 773単位 | |
| 要介護4 | 876円 | 876単位 | |
| 要介護5 | 979円 | 979単位 | |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 581円 | 581単位 |
| 要介護2 | 686円 | 686単位 | |
| 要介護3 | 792円 | 792単位 | |
| 要介護4 | 897円 | 897単位 | |
| 要介護5 | 1,003円 | 1,003単位 | |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 655円 | 655単位 |
| 要介護2 | 773円 | 773単位 | |
| 要介護3 | 896円 | 896単位 | |
| 要介護4 | 1,018円 | 1,018単位 | |
| 要介護5 | 1,142円 | 1,142単位 | |
| 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 666円 | 666単位 |
| 要介護2 | 787円 | 787単位 | |
| 要介護3 | 911円 | 911単位 | |
| 要介護4 | 1,036円 | 1,036単位 | |
| 要介護5 | 1,162円 | 1,162単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
デイサービス(通所介護)とは|利用目的や料金・利用条件まで全て解説

通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションは、リハビリが必要な方が、設備が整った施設に通いリハビリを行うことで、自立した生活への復帰を目指すサービスのことです。
介護老人保健施設や診療所・病院などで、理学療法や作業療法などのリハビリを受けます。
通所サービスの利用時間は、1時間以上から8時間未満まで、いくつかのパターンから選ぶことが可能です。要支援の方も介護予防のための機能維持を目的として活用できます。
通常規模型リハビリテーション費
| 利用する時間 | 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|---|
| 1時間以上2時間未満 | 要介護1 | 366円 | 366単位 |
| 要介護2 | 395円 | 395単位 | |
| 要介護3 | 426円 | 426単位 | |
| 要介護4 | 455円 | 455単位 | |
| 要介護5 | 487円 | 487単位 | |
| 2時間以上3時間未満 | 要介護1 | 380円 | 380単位 |
| 要介護2 | 436円 | 436単位 | |
| 要介護3 | 494円 | 494単位 | |
| 要介護4 | 551円 | 551単位 | |
| 要介護5 | 608円 | 608単位 | |
| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 483円 | 438単位 |
| 要介護2 | 561円 | 561単位 | |
| 要介護3 | 638円 | 638単位 | |
| 要介護4 | 738円 | 738単位 | |
| 要介護5 | 836円 | 836単位 | |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 549円 | 549単位 |
| 要介護2 | 637円 | 637単位 | |
| 要介護3 | 725円 | 725単位 | |
| 要介護4 | 838円 | 838単位 | |
| 要介護5 | 950円 | 950単位 | |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 618円 | 618単位 |
| 要介護2 | 733円 | 733単位 | |
| 要介護3 | 846円 | 846単位 | |
| 要介護4 | 980円 | 980単位 | |
| 要介護5 | 1,112円 | 1,112単位 | |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 710円 | 710単位 |
| 要介護2 | 844円 | 844単位 | |
| 要介護3 | 974円 | 974単位 | |
| 要介護4 | 1,129円 | 1,129単位 | |
| 要介護5 | 1,281円 | 1,281単位 | |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 757円 | 757単位 |
| 要介護2 | 897円 | 897単位 | |
| 要介護3 | 1,039円 | 1,039単位 | |
| 要介護4 | 1,206円 | 1,206単位 | |
| 要介護5 | 1,369円 | 1,369単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
デイケア(通所リハビリテーション)とは?対象者やデイサービスとの違い・選び方も解説

短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入居生活介護は、いわゆるショートステイです。
利用者は、特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、食事や入浴といった生活支援などを受けることができます。
連続利用日数は30日までですが、数日から2週間程度の利用が多くなっています。対象者は、要介護認定を受けている方です。
利用者個人の心身の状況だけでなく、家族の体調や冠婚葬祭などのために一時的に介護の継続が難しいときも、短期入所のサービスを受けることができます。
単独型短期入居生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
| 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 638円 | 638単位 |
| 要介護2 | 707円 | 707単位 |
| 要介護3 | 778円 | 778単位 |
| 要介護4 | 847円 | 847単位 |
| 要介護5 | 916円 | 916単位 |
単独型短期入居生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
| 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 638円 | 638単位 |
| 要介護2 | 707円 | 707単位 |
| 要介護3 | 778円 | 778単位 |
| 要介護4 | 847円 | 847単位 |
| 要介護5 | 916円 | 916単位 |
単独型ユニット型短期入居生活介護費(Ⅰ)
<ユニット型個室>
| 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 738円 | 738単位 |
| 要介護2 | 806円 | 806単位 |
| 要介護3 | 881円 | 881単位 |
| 要介護4 | 949円 | 949単位 |
| 要介護5 | 1,017円 | 1,017単位 |
単独型ユニット型短期入居生活介護費(Ⅱ)
<ユニット型個室的多床室>
| 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 738円 | 738単位 |
| 要介護2 | 806円 | 806単位 |
| 要介護3 | 881円 | 881単位 |
| 要介護4 | 949円 | 949単位 |
| 要介護5 | 1,017円 | 1,017単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
ショートステイとは|利用できるサービスや利用条件・料金まで全て解説

短期入所療養介護
短期入居療養介護は、介護老人保健施設、老人病院などに数日から2週間程度入居し、治療や機能訓練などを受けるサービスです。
ショートステイの1つのタイプですが、こちらのサービスは投薬やリハビリなどの医療行為の提供がメインです。
短期入居療養介護には、要介護度と4つの部屋のタイプ別にいくつかのパターンがあります。
介護老人保健施設短期入居療養介護費(ⅰ)
<従来型個室>基本型
| 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 752円 | 752単位 |
| 要介護2 | 799円 | 799単位 |
| 要介護3 | 861円 | 861単位 |
| 要介護4 | 914円 | 914単位 |
| 要介護5 | 966円 | 966単位 |
介護老人保健施設短期入居療養介護費(ⅲ)
<多床室>基本型
| 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 638円 | 638単位 |
| 要介護2 | 707円 | 707単位 |
| 要介護3 | 778円 | 778単位 |
| 要介護4 | 847円 | 847単位 |
| 要介護5 | 916円 | 916単位 |
経過的ユニット型介護老人保健施設短期入居療養介護費(ⅰ)
<ユニット型個室的多床室>基本型
| 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 833円 | 833単位 |
| 要介護2 | 879円 | 879単位 |
| 要介護3 | 943円 | 943単位 |
| 要介護4 | 997円 | 997単位 |
| 要介護5 | 1,049円 | 1,049単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
特定施設入居者生活介護
介護保険施設でなくても、都道府県から指定を受けた特定施設(後ほど詳しく説明します。)で、「特定施設入居者生活介護」というサービスを受けられます。サービス内容は、食事・入浴介助などの日常生活のサポート・介護だけでなく、リハビリ、レクリエーションなどいろいろあります。
介護サービス費は、基本的に定額です。ただ、手厚い体制をとっている介護付き有料老人ホームなどは、上乗せ介護費加算もありますので、事前に確認しましょう。
| 要介護度 | 自己負担額(円/回) ※1単位10円の地域の場合 |
単位 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,460円 | 5,460単位 |
| 要支援2 | 9,330円 | 9,330単位 |
| 要介護1 | 1万6,140円 | 1万6,140単位 |
| 要介護2 | 1万8,120円 | 1万8,120単位 |
| 要介護3 | 2万0,220円 | 2万0,220単位 |
| 要介護4 | 2万2,140円 | 2万2,140単位 |
| 要介護5 | 2万4,210円 | 2万4,210単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)
施設サービスの内容・自己負担割合
施設サービスは、施設に入居して受けることができる介護サービスです。
入居先となる施設は、介護保険施設として特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設の3つがあります。このうち、介護療養型医療施設は、2024年3月までに廃止され、新設された介護医療院へ転換されることになっています。
施設サービスは、他にもサービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループホームなどの高齢者向け住まい・施設があり、要介護度に応じて自己負担額割合が変動します。
以下では、このうち介護保険施設の特養と、特定施設、グループホームについて解説します。
特別養護老人ホーム(特養)
特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の方が入居できる施設です。食事や入浴の介助などの日常生活の支援、機能訓練や療養上のサポートを、介護保険を使って受けることができます。
利用者が負担する施設サービス費は、使用する部屋のタイプや施設の体制で違いがあります。入居の際に事前に確認しましょう。
以下は、特別養護老人ホームで受けられる介護保険サービスの、部屋タイプ別・要介護度別の自己負担額です。
<従来型 自己負担額(円)/30日>
| 要介護度 | 個室 | 多床室 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 1万7,190円 | 1万7,190円 |
| 要介護2 | 1万9,230円 | 1万9,230円 |
| 要介護3 | 2万1,360円 | 2万1,360円 |
| 要介護4 | 2万3,400円 | 2万3,400円 |
| 要介護5 | 2万5,410円 | 2万5,410円 |
<ユニット型 自己負担額(円)/30日>
| 要介護度 | 個室 | 多床室 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 1万9,560円 | 1万9,560円 |
| 要介護2 | 2万1,600円 | 2万1,600円 |
| 要介護3 | 2万3,790円 | 2万3,790円 |
| 要介護4 | 2万5,860円 | 2万5,860円 |
| 要介護5 | 2万7,870円 | 2万7,870円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
【イラストで解説】特別養護老人ホーム(特養)とは?特徴や費用・入所条件まで紹介!

特定施設
特定施設は、入居者のためのサービスを提供する都道府県の指定を受けた施設です。
特定施設には、要介護者向けの「特定施設入居者生活介護」、要支援者向けの「介護予防特定施設入居者生活介護」があります。また、同一市区町村の要介護1以上の方を対象とした「地域密着型特定施設入居者生活介護」もあります。
特定施設に該当する施設は、次の4つです。
- 介護付き有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(一部)
- ケアハウス(軽費老人ホーム)
- 養護老人ホーム
特定施設では、ケアプランの作成、食事・入浴・排泄その他の身体的介助、機能訓練などのサービスを受けることができます。
| 自己負担額(円/月) ※1単位10円の地域の場合 |
単位/月 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,460円 | 5,460単位 |
| 要支援2 | 9,330円 | 9,330単位 |
| 要介護1 | 1万6,140円 | 1万6,140単位 |
| 要介護2 | 1万8,120円 | 1万8,120単位 |
| 要介護3 | 2万220円 | 2万220単位 |
| 要介護4 | 2万2,140円 | 2万2,140単位 |
| 要介護5 | 2万4,210円 | 2万4,210単位 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
近くのサ高住・介護付き有料老人ホームを探すグループホーム
グループホームは、要支援2もしくは要介護1以上の認知症の方を対象としたケア施設です。
入居後は、施設スタッフから生活支援や機能訓練などのサービスを受けながら、最大9人のユニットで共同生活を送ります。
住み慣れた地域で暮らし続けられる地域密着型サービスの1つで、周辺の地域の人たちとの交流も盛んです。アットホームな雰囲気の中でくつろいだ生活ができます。
| 要介護度 | 1ユニット自己負担額(円/30日) | 2ユニット自己負担額(円/30日) |
|---|---|---|
| 要支援2 | 2万2,800円 | 2万2,440円 |
| 要介護1 | 2万2,920円 | 2万2,560円 |
| 要介護2 | 2万4,000円 | 2万3,610円 |
| 要介護3 | 2万4,690円 | 2万4,330円 |
| 要介護4 | 2万5,200円 | 2万4,810円 |
| 要介護5 | 2万5,740円 | 2万5,320円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
【イラストで解説】グループホームとは|サービス内容・特徴から費用・入所条件まで解説

地域密着型サービスの内容・自己負担割合
地域密着型サービスは、介護が必要になったときに、できるだけ住み慣れた地域で身近な人に介護してもらえるようにとのねらいで、2006年に作られた制度です。
自治体にサービス基準等の設定が任せられており、地域の実情にあう運用ができます。
ただし、あくまでも、自宅生活する場合に利用できるサービスが対象です。住んでいる地域以外では、サービスを受けられません。
また、グループホームや特養、ケアハウス、介護付き有料老人ホームなどを短期利用できますが、長期利用は対象外です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護職員と看護師が連携して、24時間切れ目なく訪問介護・看護を提供するサービスです。
たとえば、ひとり住まいの方は、薬の管理やトイレ介助など、短時間のケアを日に複数回受けることもできます。
また、緊急時には、電話などの通報で随時対応も受けられます。事業所を各地域に設置して、通報があればおよそ30分以内に駆けつけられる体制を推進しています。
<訪問看護サービスを行う看護師などがいる事業所の場合(一体型)>
- 訪問介護サービスを行わない場合
| 要介護度 | 自己負担額(円/月) |
|---|---|
| 要介護1 | 5,697円 |
| 要介護2 | 1万168円 |
| 要介護3 | 1万6,883円 |
| 要介護4 | 2万1,357円 |
| 要介護5 | 2万5,829円 |
- 訪問看護サービスを行う場合
| 要介護度 | 自己負担額(円/月) |
|---|---|
| 要介護1 | 8,312円 |
| 要介護2 | 1万2,985円 |
| 要介護3 | 1万9,821円 |
| 要介護4 | 2万4,434円 |
| 要介護5 | 2万9,601円 |
<訪問看護サービスを行う看護師などがいない事業所の場合(連携する別の事業所が訪問看護サービスを実施)(連携型)>
| 要介護度 | 自己負担額(円/月) |
|---|---|
| 要介護1 | 5,697円 |
| 要介護2 | 1万168円 |
| 要介護3 | 1万6,883円 |
| 要介護4 | 2万1,357円 |
| 要介護5 | 2万5,829円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問看護は、夜間に訪問介護を受けることができるサービスです。
夜間に定期的に訪問介護員が利用者の家を訪れる「定期巡回」と、「随時対応」サービスがあります。
「定期巡回」は、トイレ介助やおむつ交換などの介護サービスを行います。「随時対応」は、緊急時に利用者の求めがあれば、すぐに介護に向かいます。
定期巡回・随時対応型介護看護との違いは、夜間だけに対応するサービスという点です。
| 項目 | 自己負担額(円/回) |
|---|---|
| 基本利用料 | 1,025円 |
| 定期巡回サービス | 386円 |
<随時訪問サービスの場合>
| 介護員の人数 | 自己負担額(円/回) | |
|---|---|---|
| 訪問介護員が1人で訪問した場合 | 588円 | |
| 訪問介護員が2人で訪問した場合 | 792円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
地域密着型通所介護は、利用者ができるだけ自立した日常生活を自宅で送ることができるように、孤立感の解消や心身機能の維持を図ります。また、家族の介護の負担を軽減することも目的です。
地域密着型通所介護施設は、利用定員が18人以下のデイサービスセンターなどです。
比較的小規模な施設で、利用者の送迎、食事・入浴、その他の生活支援や、機能訓練などのサービスを日帰りで実施しています。
| 利用する時間 | 要介護度 | 自己負担額(円/回) |
|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 415円 |
| 要介護2 | 476円 | |
| 要介護3 | 538円 | |
| 要介護4 | 598円 | |
| 要介護5 | 661円 | |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 435円 |
| 要介護2 | 499円 | |
| 要介護3 | 564円 | |
| 要介護4 | 627円 | |
| 要介護5 | 693円 | |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 655円 |
| 要介護2 | 773円 | |
| 要介護3 | 893円 | |
| 要介護4 | 1,010円 | |
| 要介護5 | 1,130円 | |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 676円 |
| 要介護2 | 798円 | |
| 要介護3 | 922円 | |
| 要介護4 | 1,045円 | |
| 要介護5 | 1,168円 | |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 750円 |
| 要介護2 | 887円 | |
| 要介護3 | 1,028円 | |
| 要介護4 | 1,168円 | |
| 要介護5 | 1,308円 | |
| 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 780円 |
| 要介護2 | 922円 | |
| 要介護3 | 1,068円 | |
| 要介護4 | 1,216円 | |
| 要介護5 | 1,360円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
小規模デイサービス(地域密着型通所介護)とは|サービス内容や料金・利用条件も解説
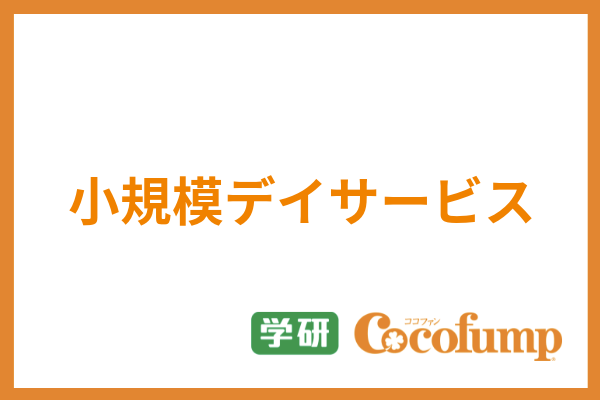
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は、認知症と診断された方が、老人デイサービスセンターや、特養老人ホームなどの施設に通って受けるサービスです。
日帰りで、認知症の方の送迎、食事・入浴・トイレ介助などの介護や機能訓練をスタッフが提供してくれます。
一般のデイサービスとの違いは、定員が少ないことと、利用者が認知症の方になることです。
| 利用する時間 | 要介護度 | 自己負担額(円/回) |
|---|---|---|
| 3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 542円 |
| 要介護2 | 596円 | |
| 要介護3 | 652円 | |
| 要介護4 | 707円 | |
| 要介護5 | 761円 | |
| 4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 568円 |
| 要介護2 | 625円 | |
| 要介護3 | 683円 | |
| 要介護4 | 740円 | |
| 要介護5 | 797円 | |
| 5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 856円 |
| 要介護2 | 948円 | |
| 要介護3 | 1,038円 | |
| 要介護4 | 1,130円 | |
| 要介護5 | 1,233円 | |
| 6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 878円 |
| 要介護2 | 972円 | |
| 要介護3 | 1,064円 | |
| 要介護4 | 1,159円 | |
| 要介護5 | 1,254円 | |
| 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 992円 |
| 要介護2 | 1,100円 | |
| 要介護3 | 1,208円 | |
| 要介護4 | 1,316円 | |
| 要介護5 | 1,424円 | |
| 8時間以上9時間未満 | 要介護1 | 1,024円 |
| 要介護2 | 1,135円 | |
| 要介護3 | 1,246円 | |
| 要介護4 | 1,359円 | |
| 要介護5 | 1,469円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護では、家への訪問と、小規模な施設の日帰り利用と宿泊を組み合わせたサービスを受けられます。
また、生活支援、食事や入浴・排泄の介助といった介護サービスなどを総合的に受けることができます。
普段は自宅で過ごし、体調の悪い時などは24時間見守りのある泊まりにするなど、柔軟にご利用いただくことが可能です。ただ、看護師が常駐しているわけではないので、医療的ケアは限られます。
| 要介護度 | 自己負担額(円/月) |
|---|---|
| 要介護1 | 1万423円 |
| 要介護2 | 1万5,318円 |
| 要介護3 | 2万2,283円 |
| 要介護4 | 2万4,593円 |
| 要介護5 | 2万7,117円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問介護を合わせたサービスです。
要介護1以上の方が利用でき、要支援の方は利用できません。
小規模多機能型居宅介護に、看護が加わった複合サービスです。小規模多機能型居宅介護と同様の生活支援や介護サービスを受けることができます。加えて、利用者が必要とする医療ケアも提供してもらえます。
| 要介護度 | 自己負担額(円/月) |
|---|---|
| 要介護1 | 1万2,438円 |
| 要介護2 | 1万7,403円 |
| 要介護3 | 2万4,464円 |
| 要介護4 | 2万7,747円 |
| 要介護5 | 3万1,386円 |
出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造(令和3年4月施行版)」
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)とは|利用条件や費用まで全て紹介

自己負担割合はいつ決まるの?
介護保険サービスの利用料金は、自己負担額と介護給付で賄われます。利用者の自己負担額は、料金の1割・2割・3割のいずれかに決まっており、この割合が「自己負担割合」です。
介護保険の自己負担割合の決定時期について、詳しく見ていきましょう。
要介護認定・負担割合証発行で決まる
要介護認定の申請をすると、約1か月で介護認定がなされます。
また介護保険の自己負担割合は、この要介護認定の際に前年の所得をもとに決定されます。
それを受けて、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が発行され、送られてきます。
この介護保険負担割合証に自己負担割合が記載されています。本人が自分の自己負担割合を把握できるのは、介護保険負担割合証が送られてきた時点です。
負担割合証はいつ更新される?
負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。
毎年自動で更新され、7月下旬に新しい負担割合証が市区町村から送られてきます。自動更新の対象は、5月末時点で要介護認定を受けている方です。
負担割合は、所得や世帯構成の変化に伴い1割から3割の間で随時見直されます。
変更があった場合は、その都度、新たな負担割合証が交付されます。負担割合証の更新・変更があった場合は、ケアマネージャーに必ず知らせましょう。
負担割合証は各種サービスの利用で必要
介護保険負担割合証は、さまざまな介護サービスを利用するときに、介護保険被保険者証と一緒に必ずサービス事業者や利用施設に提示する必要があります。
ですから、介護保険被保険者証とともに大切に保管しておきましょう。サービス利用時には必ずセットで持参し、提示できるようにしておくと良いです。
また、負担割合証の一部でも変更があった場合は、必ずサービス提供事業所・利用施設にもその旨伝えましょう。
介護費用の負担を減らす方法・制度
ここでは、介護費用の負担を減らす方法・制度を紹介します。自己負担額が高額になった場合の軽減措置はいくつかありますので、活用しましょう。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は、決められた自己負担額の上限を超えた場合に、超えた分が介護保険から支払われる制度です。
介護サービス利用料の1か月の自己負担上限額は、個人または世帯の所得区分に応じて決まっています。
上限額を超えた分は、自治体への申請により「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。自動で返金支給されるものではないので、申請し忘れないように注意しましょう。
| 区分 | 対象 | 負担上限額(月額) |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護の受給者等 | 15,000円(個人) |
| 第2段階 | 前年の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計が年間80万円以下の場合 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 第3段階 | 世帯の全員が市区町村民税を課税されていない世帯 | 24,600円(世帯) |
| 第4段階 | 市区町村民税課税世帯で課税所得が380万円未満の世帯 | 44,400円(世帯) |
| 第5段階 | 市区町村民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円未満の世帯 | 93,000円(世帯) |
| 第6段階 | 市区町村民税課税世帯で課税所得が690万円以上の世帯 | 140,100円(世帯) |
注1:「世帯」は介護サービスを利用した世帯員全員の負担合計の上限額、「個人」は介護サービスを利用した本人の負担上限額です。
注2:第5・第6段階は、2021年8月のサービス利用分から追加されたものです。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度は、医療保険と介護保険の1年間の自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、自己負担額を軽減する制度です。
世帯ごとに集計され一定の限度額を超えた負担額が、申請によって払い戻されます。
また、申請できる世帯には条件が存在します。具体的には、各医療保険における世帯内で、自己負担合算額が所得区分ごとに設定された限度額を超えた世帯です。
軽減額は、合算対象期間がいつからかにより決まりますが、毎年8月1日から翌年7月31日までです。支給対象になると通知が来ます。申請には本人確認、振り込み口座の記載が必要です。
居住介護住宅改修費・リフォーム・福祉器具
居住介護住宅改修費・リフォーム・福祉器具の購入費用などにも、介護保険が使えます。
対象になる住宅改修工事は、手すり取付け・段差の解消・開き戸から引き戸への取換え・和式から洋式への便器換えなどです。
住宅改修にかかる費用の上限額は、要介護区分に関係なく、20万円 (1割~3割負担)です。利用する際は、事前申請が必要です。基本的に工事の際に全額支払い、後から返ってくる仕組みになっています。
特定福祉用具購入
特定福祉用具とは、排泄や入浴などに使用する用具で、貸与になじまないものです。腰掛便座、椅子・浴槽手すりなどの入浴補助用具、簡易浴槽などが該当します。
特定福祉用具は、指定された事業所での購入に限り、介護保険を利用でき、代金の一部が返ってきます。
ただし、同じものは1つしか購入できません。また、1年につき10万円(1割~3割負担)が支給上限額です。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費は、一定の負担限度額を超えた居住費と食費が介護保険から支給される制度です。利用する際は、市区町村で負担限度額認定を受けなければなりません。
対象者は、所得や資産が一定以下で、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入居している人です。
負担限度額は、入居者の所得段階、施設の種類や部屋タイプによって異なります。
医療費控除
医療費控除は、年間の医療費の自己負担額が一定額以上の場合に、所得控除を受けられる制度です。
通常の医療費だけでなく、居宅サービスなどの一部の介護保険サービスの自己負担分や、特別養護老人ホームなどの居住費や食費、おむつ代(医師の証明がある場合)も控除対象になります。
居宅サービス事業者等の領収証に医療費控除の対象額が記載されますので、確認しましょう。
介護施設の利用費を抑えることも重要
介護で最も費用の負担が大きいのは、やはり介護施設の利用費でしょう。ここを如何に抑えられるかによって、介護の費用負担の度合いが大きく変わってきます。
公的施設を利用することができれば費用を軽くできますが、特養を始めとしてこれらの施設は入所待機者が非常に多いため、民間施設の利用も同時に検討することが必要になります。
学研ココファンのサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは、入居金が0円であったりと費用を大幅に削減できる上に、必要なサービスを厳選して利用することができますので、ぜひチェックしてみてください。
ココファンのサ高住・有料老人ホームを探す介護保険の負担割合についてまとめ
- 負担割合は1割〜3割であり、要介護認定後に発行される負担割合証に記載されている
- 介護保険適用サービスには、訪問・通所・短期入所介護などの居宅サービス、特養・老健などの施設サービス、地域密着型サービスなどがある
- 介護費用負担を減らす方法として、高額介護サービス費、高額医療・高額介護合算制度、居住介護住宅改修費などがある
介護保険の負担割合について、サービス内容ごとの利用条件、計算方法、自己負担額の目途などと共に解説しました。
介護保険サービスは、要介護度に応じて様々なサービスから必要なものを選んで使うことができます。
その際には、自己負担の仕組みや限度額をきちんと理解しておくことが大事です。この記事を参考にしてぜひ上手に活用してください。
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。
監修した専門家の所属はこちら









