認知症の入院費用は?検査・治療の負担割合から医療費を抑えられる制度まで全て紹介
更新日時 2023/08/07
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
「親が認知症なんだけど、入院できるのかな?」
「親が入院することになったとしても、お金がないから入院費が払えない・・・」
このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
親御さんなどご家族が認知症である場合、入院も選択肢として考えるのではないでしょうか。
そもそも認知症で入院することはできるのか、入院費用はどのくらいかかるのか、払うことができるのかなど、不安でいっぱいな方も多いでしょう。
そこで、この記事では認知症で入院する場合の費用について詳しくお伝えします。
入院する場合の費用はどのくらいか、認知症で入院する場合の費用の内訳、入院費が払えないときの対処法など、ご家族が認知症である場合知っておきたい情報を解説します。ぜひ参考にしてみてください!
- 認知症で入院する場合は精神科がメイン
- 認知症で入院する際、費用の平均は月7万円
- 自立支援医療などの制度を使えば、費用が抑えられる
そもそも認知症で入院はできる?
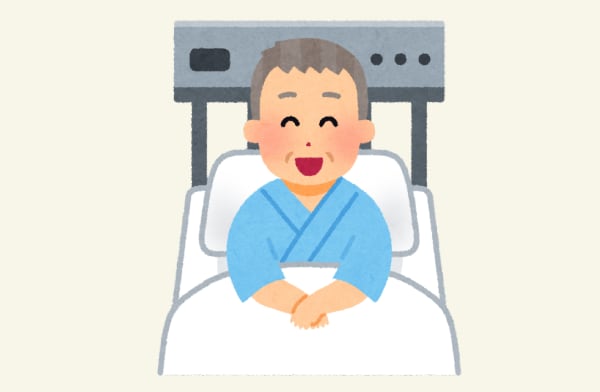
認知症で入院する場合は、主に精神科に入院しますが、一部の病院では「もの忘れ外来」「メモリークリニック」など、認知症の専門外来もあります。
認知症で入院するケースでよくあるのは、自宅や施設での介護が難しくなったとき、怪我などで緊急搬送されたときです。
あるいは、高度な認知症状や行動の問題がある場合、身体的な合併症がある場合など、自宅や施設でのケアが難しいケースもあります。
厚生労働省「平成25年度老人保健健康増進等事業」の一環である、富士通総研による「認知症の人の精神科入院医療と在宅支援のあり方に関する研究会」によると、認知症の人の精神科病院への入院が必要な状態とは以下のような状態です。
精神保健福祉法に則って、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる場合に加えて、
出典:株式会社富士通総研
(Ⅰ)妄想(被害妄想など)や幻覚(幻視、幻聴など)が目立つ
(Ⅱ)些細なことで怒りだし、暴力などの興奮行動につながる
(Ⅲ)落ち込みや不安・苛立ちが目立つ
ことにより、本人および家族など介護者の生活(睡眠・摂食・就労など)等が阻害され、非薬物的療法では改善がみられず、拒薬や治療拒否があり、薬剤調整など認知症を専門とする医師による入院医療が必要とされる場合と考えるものとした。
精神科では通院による自立支援も
精神科などでは、自立支援医療という制度があります。
これは
- 精神通院医療
- 更生医療(身体障害)
- 育成医療(身体障害)
の3つが対象で、一定の条件に当てはまる方は、その方の所得によって医療費の一部を国が負担するため、ご本人の医療費の負担が軽減されるというものです。
原則は1割負担となり、病院と薬局で支払う額の上限が所得によって定められます。上限を超えた分は支払う必要はありません。
具体的な所得に応じた医療費の負担割合や上限額は、地域や施設によって異なる場合がありますので、詳細な情報は専門の機関や病院に問い合わせるとよいでしょう。
認知症で入院する際の費用は?
認知症で入院する場合、自己負担額では平均して月7万円ほどかかります。
この7万円とは、入院費用のみの額です。 これに加え、入院中の生活費や日用品費などがかかるため、総額ではもう少し高くなります。
ただし、入院費用は
- 個室か大部屋か
- 医療保険の自己負担割合
この2点によって大きく異なります。
他にも、些細な違いではありますが、利用する設備・サービスによってや、入院する病院が公立か民間かによっても費用は変動します。
さらに、入院期間は人それぞれであるため、短ければ費用は安く済み、長くなればなるほど費用は増えていきます。
具体的な費用については、入院する病院のソーシャルワーカーやケースワーカーなどの職員に聞いてみましょう。
特に高齢者の場合、リハビリなどで入院期間が長引くことが多いため、費用が高めになる傾向があります。この点にも注意しましょう。
認知症対応可能な介護施設はこちら!認知症にまつわる全般的な費用
認知症になって入院した場合、どのくらいの費用がかかるのか、目安として草津病院の例を参考にして、表にまとめました。
| 保険・負担の種類 | 詳細な内容 | 医療費 | 食事 |
|---|---|---|---|
| 社会保険 国民健康保険 |
保険診療の3割 | 1食あたり460円 非課税世帯の方は限度額認定証の提出があった場合は別途料金となります |
|
| 前期高齢者(70歳以上) 後期高齢者(75歳以上) |
保険診療の1~3割 | 同上 | |
| 公費医療負担 | 特定疾患 | 特定疾患医療受給者証に記載されている金額を負担する | 無料 |
| 生活保護 | 無料(一部の人は負担金あり | 無料 | |
| 原爆被爆者 | 無料 | 無料 |
参考:草津病院
このように、70歳未満、70歳以上74歳、75歳といった年齢区分で医療費の自己負担割合がかわります。
また、特定疾患をお持ちの方は、医療費は一部負担がありますが、食事は無料です。
生活保護を受けている方、原爆被害者の方は、生活保護の一部の方を除き、医療費・食費ともに無料となります。
事前の認知症検査費
入院するにあたり事前に認知症の検査をしますが、それにも費用がかかります。MRI検査や心理検査などを行い、認知症であることの確定診断が必要です。
ただ、検査は医療保険の適用範囲であるため、その医療保険で定められた自己負担割合によって検査費用が決定します。3割負担の場合は、検査の内容にもよりますが、数千円から数万円です。
治療費
病院に支払う治療費は当然必要です。病院の規模や入院期間によって1日あたりの入院基本料が定められており、それに入院日数がかかります。
公的医療保険により、原則的に負担割合は現役世代の場合3割負担、70~74歳は2割負担、75歳以上は1割負担です。 ただし、70歳以上でも現役並みの収入がある方は3割負担となります。
また、治療費を支払う際は、高額療養費制度というものがあることを知っておきましょう。
これは、収入によって医療費負担の上限が決まっており、その上限を超えた分が戻ってくるという制度です。
差額ベッド代
通常は大部屋に入院します。しかし、個室や少人数の部屋を希望する場合は、差額ベッド代がかかります。差額ベッド代は公的医療保険の適用外であるため、全額自己負担となります。
厚生労働省の「中央社会保険医療協議会 総会(第401回)主な選定療養に係る報告状況」(平成30年)によると、1日あたりの差額ベッド代の平均は6188円です。
食事代
入院中の食事代の自己負担額は全国一律であり、1食あたり460円と決められています。
食事代は、公的医療保険の自己負担軽減の対象とはなりません。ただし、住民税非課税世帯の方は、例外として食事代が下がります。
また、先ほど述べたように、特定疾患のある方、生活保護を受給している方、原爆被害者の方は、食費は無料です。
交通費
入院中は、家族が面会で病院に訪れる機会が多くなります。その際の電車代、バス代、車で来る歳のガソリン代など、交通費も念頭に置いておくことが必要です。
このような交通費を使うのはご家族であり、ご本人ではないため医療費控除の対象にもならず、自己負担となります。
入院が長期に渡れば渡るほど交通費の負担は大きくなります。交通費についてもあらかじめ用意しておくことが必要です。
生活費
入院中の冷蔵庫、テレビ、テーブルなどの使用料金、クリーニング代、洗面用具、下着など、生活にかかる費用も自己負担です。
在宅の状態から入院になった場合には、この生活費も入院によって追加でかかる費用として負担になります。
病院によって生活用品の使用料などは異なるため、入院前にしっかりチェックしておきましょう。
知人等のお見舞いへのお礼
入院中に知人などからお見舞いの品をもらった場合、退院時にお礼を贈ることも考えておきましょう。
お礼をお返しするのは必須ではありませんが、一般的にはお礼をお返しする人も多くいます。
お見舞いへのお礼は一つ一つは小さな額でも、お見舞いの品が多ければ、お返しも大きな額になります。
金額の目安としては、いただいた品と同等の金額である必要はありませんが、一般的には3分の1から2分の1相当の品物をお返しとして贈る傾向があります。
高齢者施設等の介護費用
認知症の症状が改善し、退院したあとは高齢者施設に入所することが多くなります。
施設によって費用は大きくことなるため、各施設でかかる費用の目安をご紹介します。施設での費用と入院費との比較も見てみましょう。
公的施設の目安の費用
| 種類 | 費用(初期費用) | 費用(月額費用) |
|---|---|---|
| 特別療養老人ホーム | 0 | 5万~15万円 |
| 介護老人保健施設 | 0 | 8万~14万円 |
| 介護療養型施設 | 0 | 9万~17万円 |
| 軽費老人ホーム | 0~数十万円 | 10~30万円 |
公的施設は、初期費用が少ないところが多く、費用を抑えられる点が魅力です。
民間施設の目安の費用
| 種類 | 費用(初期費用) | 費用(月額費用) |
|---|---|---|
| 介護付き老人ホーム | 0~数百万円 | 15万~30万円 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0~数百万円 | 15万~30万円 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 0~数十万円 | 10万~30万円 |
| グループホーム | 0~数十万円 | 15~20万円 |
民間施設の中でも、費用をある程度抑えられる施設も存在します。
結局どれを選ぶと良い?
施設入居でかかる費用を全体的にみると、公的施設の方が安くなります。 しかし、公的施設は入居条件が要介護3以上であったりと厳しく、また入居待機者も多いことから利用までが難しいのです。
一方、民間施設は公的施設よりも費用は高くかかってしまいますが、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などではより融通が効きやすく、それぞれの介護度に合わせた適切なサービスを受けることが出来ます。
また、認知症介護に特化したグループホームも、人気の高い施設ですのでおすすめです。
学研ココファンでは、サービス付き高齢者向け住宅をはじめとした様々な介護施設を、全国各地に配置しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
近くの学研の介護施設を探す!在宅介護でかかる費用
高齢者施設を利用せずに在宅介護のみ行う場合、毎月の費用は平均5万円ほどになります。
具体的には、訪問介護や通所介護などの介護サービス利用費で1万5千円程度、介護サービス以外の費用は平均で3万5千円ほど必要です。
介護にかかる費用は、要介護度によって変わります。 そのため、要介護4、要介護5の方はより高い費用になり、要支援1、要支援2の方は安い費用になります。
要介護や要支援の度合い、介護サービスの利用状況に合わせて、適切なプランを立てることがとても大切になります。
お金がない・入院費が払えないときは?
認知症での入院費用がなく、入院費が払えないときにはどうすればよいのでしょうか。いくつかの方法がありますので、利用できる方法を活用しましょう。
病院に相談する
まずは、入院先の医療機関に相談するのがよいでしょう。
規模の大きな病院には、ソーシャルワーカーやケースワーカーが在籍しています。そのような職員に相談すれば、医療保険の利用法について教えてくれます。
また、分割払いや支払い期限の延長など、支払い方法に配慮してもらえる場合もありますので、まずは相談することがおすすめです。
高額療養費制度を確認する

高額療養費制度とは、先ほども述べたように、一ヶ月にかかった医療費の自己負担限度額を超えたとき、その超えた分の金額が戻ってくる制度です。健康保険など、公的医療保険に加入していれば誰でも使うことができます。
自己負担額の上限は収入によって異なりますので、詳しく知りたい場合は病院のソーシャルワーカーなどの職員や、お住まいの自治体の担当者にご確認ください。
その他の制度も合わせて利用する
高額療養費制度の他にも、使える制度はいくつかあります。これらの制度も合わせて利用すれば、費用の問題が解決する可能性が高くなります。
便利な制度がいくつか存在するため、それぞれについて押さえておきましょう。
限度額適用認定証
入院費用が高額になる場合、加入している医療保険に申請をすることにより 「限度額適用認定証」 が発行されます。
通常、高額療養費制度では、かかった費用についてまずは3割負担額を支払い、後日自己負担限度額を超えた分が戻ってくるという手順になっています。
しかし、この「限度額適用認定証」を事前に病院に提出することにより、入院費用は3割負担ではなく自己負担限度額のみ支払えばよくなるため、高額療養費制度を利用しても費用が払えないとお困りの方におすすめの制度です。
高額介護サービス費
要介護者はそれぞれ介護サービス費の自己負担額が決まっています。高額介護サービス費とは、介護サービス費が自己負担額を超えてしまった場合に、超えた分が後日戻ってくるという制度です。
それぞれの所得による負担限度額は、令和3年8月以降は以下の通りになりました。
| 区分 | 詳細 | 負担の上限額(月額) |
|---|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,200円(世帯) | |
| 課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
| 市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) | |
| 世帯の全員が市町村民税非課税 | 前年の公的年金等収入金額プラスその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
高額介護サービス費を支給されるためには、お住まいの自治体に申請する必要があります。
高額医療費貸付制度
高額療養費制度を利用しても、限度額を超えた分の返金には3ヶ月ほどかかってしまいます。
その間の経済的負担を軽減するため、高額医療費等貸付制度があります。これは、高額療養費制度での限度額が返金されるまでの間の医療費などにかかる費用を、無利子で貸付するものです。
ただし、一カ月の医療費が自己負担分の限度額を超えた場合に利用できるなど、条件がある点には注意が必要です。

 老人ホーム・介護施設を探す
老人ホーム・介護施設を探す
親の入院に備えて注意すべきポイント
実際に、親が認知症で入院することになったら、どうすればよいのでしょうか。
入院が決まったときには、注意すべきポイントがいくつかあります。実際に入院することになる前に確認しておかないと、親の認知症が進行し記憶があいまいになり、準備ができなくなる事態も考えられます。
以下のポイントについて、あらかじめ確認しておきましょう。
印鑑や通帳・保険証などの準備
印鑑、通帳、保険証は各種手続きに必要になります。例えば、入院時にはご家族の印鑑だけではなく、ご本人の印鑑も必要になるのが一般的です。
また、ご本人の保険証は入院時や役所での手続きの際に必要です。通帳も、ご本人の預金を使う場合には、保管場所がわからないと困ってしまいます。これらは事前に準備しておくことをおすすめします。
また、口座には十分なお金が入っているのかもあらかじめ調べておいた方がよいでしょう。
大切な書類を整理・管理し、必要な時にスムーズに利用できるよう家族のサポートも大切になります。
服用薬や持病について確認する
親の持病については必ず把握しておきましょう。また、服用薬の内容や、薬の保管場所も親に聞いておく必要があります。
もし服用薬の内容を知らないと、病院で治療を受ける場合や入院の際、投薬ができず困る可能性があります。
お薬手帳をお持ちの方の場合は、手帳を見ればどのような薬を服用しているのかわかりますので、まずはお薬手帳があるか確認してみましょう。
お薬手帳を持っていなければ、親のかかりつけの病院に確認するなどして、服用薬については正確に把握しておくことが必要です。
加入している保険について確認する
民間の医療保険や介護保険に加入していた場合、入院することにより入院費が出ることがあります。
親が何の保険に入っているのか、保険の契約内容はどうなっているのかをよく確認し、入院費が出るのかどうか把握しておくことが大切です。
また、実際に入院費が出る場合、保険会社とやり取りをするのはご本人ではなくお子さんの方であることが多いですので、やり取りがスムーズに進むよう、契約内容や入院費が出る条件などをよく調べておきましょう。
認知症対応可能な介護施設はこちら!認知症で入院するときの費用についてまとめ
- 入院前の検査費用は、3割負担の場合数千演から数万円
- お金がないので入院費が払えないときは、高額療養費制度、限度額適用認定証などさまざまな制度を利用しよう
- 親の入院に備えて、印鑑や通帳の場所や、普段服用している薬などを把握しておこう
親など、高齢者のご家族が認知症になり入院することになった場合、さまざまな費用がかかります。
もし入院費用が支払えない場合は、病院に相談したり、自治体の制度を活用したりなどすれば費用を抑えることが可能で、入院費を払える可能性が高まります。
今から準備をしておき、いつご家族が入院することになっても慌てずに対応できるようにしましょう!
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。
監修した専門家の所属はこちら









