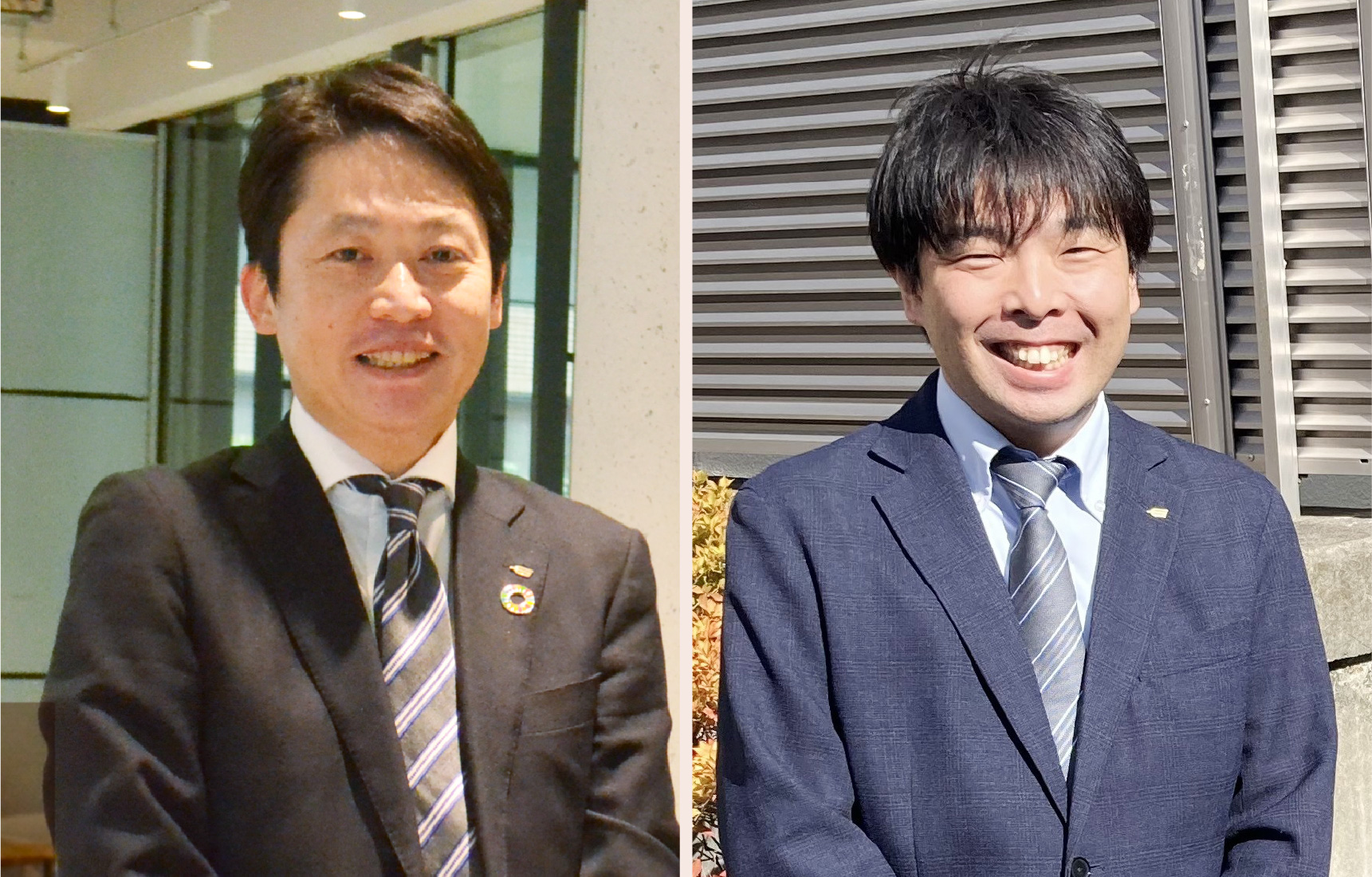


STORY
第1号拠点の
オープン

取締役 / 事業本部長
チャレンジ精神こそが学研ココファンの成長の核であり、アイデンティティー
「学習」「科学」から、介護の新規事業へ

私はいわゆる「就職氷河期」世代で、1997年の入社です。マスコミに憧れる編集者志望の学生でしたが、学習研究社(当時)の面接では「営業でもなんでもやります」とアピールしました。編集よりも営業のほうが入りやすいと聞いていたからです。学研は名が知れた大手ですし、とにかく潜り込めれば、と考えていました。
入社後は営業に配属されて7年間、当時の学研の看板商品だった「学習」「科学」の営業に携わりました。「学研のおばちゃん」と呼ばれる販売員に営業を指導するインストラクターの仕事にも従事していました。
「学習」「科学」で一時代を築いた学研でしたが、私が入社した頃には少子高齢化などの理由から本が売れなくなって久しく、たいへん厳しい状況にありました。入社の翌年には全国各都道府県に47支社あった営業の出先が5支社となり、ボーナスもどんどんカットされて。競合の会社が急激に伸びていく中、もう旧来のやり方ではダメだ、というのは誰の目にも明らかでした。
「学研で介護の新規事業をスタートする。ついては事業所の所長を募集する」という社内公募に手を挙げたとき、私は20代半ばでした。介護や福祉に特段の知見があったわけではありません。でも、停滞感のまっただ中にいて、とにかく新しい事業にチャレンジしたかったのです。やる気をアピールするためには資格ぐらい持っていないとダメだろうと、働きながらひそかに学校に通い、「ヘルパー2級」(現在の「初任者研修」)も取得しました。
社内公募に飛びついた理由は、もう一つありました。この新事業は、営業の上司である小早川さん(学研ココファン・現CEOの小早川仁)が立ち上げたものだったのです。小早川さんは私より6歳年上で、当時は30代前半。その頃からズバ抜けたカリスマ性で、若手社員の憧れでした。私が平社員で、小早川さんが課長、五郎丸さん(学研ココファン・前社長の五郎丸徹)がリーダーという3人だけの部署で仕事をしたこともありました。さまざまなジレンマを抱えつつも、どうしたらお客さまを獲得できるのかを一生懸命考え、毎晩10時ごろまで一緒に仕事をしては11時半ごろまで居酒屋で飲む。それが日課でした。尊敬する先輩と濃密な時間を共にしながら、私は、その背中をずっと追いかけてきました。新所長の適任者がいるとすれば「自分だろう、それは!」と勝手に思い込んで応募したのです。
でも、今思うと、そんな奇特な人は実は私のほかに誰もいなかったのかもしれません。皆、「出版社の社員」の感覚でしたから。介護事業なんて、当時の学研の文化からすれば、まずありえないことだったんです。
学研ココファンの夜明けと「暗黒」時代

私が教育から介護へと異動した半年後の2005年3月、学研ココファンの「原点」ともいうべき、居宅介護支援・訪問介護を提供する事業所「ココファン南千束」の立ち上げが行われました。介護の素人による一からのスタートでしたが、不安よりも「やってやる!」という気持ちのほうが大きかったですね。スタッフを採用しようにも介護の人脈など何もなかったので、私が通っていたヘルパーの学校の先生に頼んで、ケアマネとサ責(サービス提供責任者)を紹介してもらいました。小早川さんと私で三軒茶屋のミスタードーナツまで採用予定の人に会いに行ったことを覚えています。
当初は、スタッフに私の言うことを聞いてもらうのが難しく、どうしたらいいのか悩みました。それはそうだと思います。知識も技量もない。それで肩書だけは「所長」でしたから。
外回りは得意だったので、とりあえず営業に打ち込みました。そして1カ月後、ついに新規の依頼が来たのです。本当に嬉しかった。ところが、一緒に喜んでくれるはずのケアマネは「それ、要支援の人ですよね?」って渋い顔をするのです。要介護度が低いと提供サービスが少なく売り上げに繋がらないと言うことなのですが、「お客さまがいない今は何でもやるべきじゃないの?」って、すごくショックでした。
介護業界のさまざまな「常識」を私が知るのは、もう少し後になってからでした。ですが、20年たった今振り返ると、そのときの私の感じた「違和感」は、結果的には正しかったように思います。「お客さまを獲得する」とか「来たお客さまは絶対に断らない」とか、そういう営業仕込みの感覚や発想は、結局そのあともずっと学研ココファンのカラーとして受け継がれていくのです。
事業所の立ち上げから1年後の2006年3月、学研ココファンが提供する高齢者専用賃貸住宅の第1号店「ココファンレイクヒルズ」が東京都大田区にオープンしました。といっても、現在のような会社組織の体にはほど遠く、私自身が若かったこともあって、スタッフは部下というよりは仲間の感覚でした。「よし、みんなで一緒にやろうぜ!」と、まるで部活のようなノリで。ヘルパーさんがいないときは私がケアに入ることもありました。通院介助をしたり、利用者さまのお宅に出向いてトマトの湯むきをしたり、できることはなんでもしました。
今、新任所長研修で私が必ず言うことなのですが、介護の現場では、上司・部下の関係ではなくて、仲間内のリーダーにならなくてはダメ。いくら正しいことを言っても仲間ではない人が旗を振っていては誰もついてきてはくれません。命令するのではなく一緒にやる。それが、所長時代の経験から私が学んだことです。
ただひたすら「がんばります!」とがむしゃらであれば良かった私に「暗黒」が訪れたのは今から10年以上前、会社ができて7~10期目の頃でした。所長職を離れて本社に異動し、まさにこれから事業を拡大していこうという時代。ただ、社内の人的なリソースはまだ圧倒的に少なくて、当時の私はほとんどの仕事を自分一人で抱え込んでいたのです。お客さまが入らないまま加速度的に新規出店が続き、その結果、赤字はみるみる拡大していきました。とても、もう私一人の手に負えない。進退も考えましたが、やめるにやめられず、30代半ばの私は、もう八方ふさがりの状態でした。当時の会社の経営体制はまだ脆弱で、組織が抱える問題を解決できるような状態ではなく。結局、五郎丸さんが呼び戻され、分業体制が整備されて、何年もかけてやっと今の状態にまで持ち直しました。
よくここまで順風満帆な道のりであるかのように言われるのですが、それは大きな誤解です。「新卒で学研に入って、新規事業でうまく当てた」のようにも言われることがありますが、「自分はそんなイージーな道を歩んできていない!」と心から主張したいぐらいです。 考えてみればこの20年、私と学研ココファンのアップダウンは完全にリンクしてきました。学研ココファンの業績の推移を示した折れ線グラフがあるのですが、実はあれ、そのまま私そのものだと思います。
次の20年のテーマは「満足から感動へ」

会社組織が大きくなるにつれて、「前例がない」「自分の担当じゃない」「教えてもらってない」という声が聞こえてきます。でも、学研ココファンは、自分たちで工夫して何もないところから作りあげてきた、そういう会社。チャレンジ精神こそが学研ココファンの成長の核であり、アイデンティティーなのだと、そんな思いが私には強烈にあるんです。所長の仕事が大変だと聞くたび、「いや、いま自分が所長をやりたいぐらい。どんな成果が出るかやってみたい」と、そう思います。
振り返れば、事業所をオープンしたばかりの頃、地域の介護事業者の集まりに出ても「学研の介護」なんて誰も知らなくて。「えっ? 学研ココ……なんですか?」って。挨拶するのも名刺を出すのも恥ずかしくて。マイナーな事業社だということが、すごくコンプレックスでした。介護事業のこのアウェー感をなんとか克服してやろうと、自分を売り込んで、顔を覚えてもらって、そのうち「学研さん、最近よく来ますよね」って言われるようになっていきました。
あれから20年。ココファンの高齢者住宅は全国約200拠点に増えました。ココファンのブランドが確立し、「学研の介護」が多くの人に知られるようになって、学研社内でもやっとココファンの存在が認められるようになってきました。
学研は今期(79期)の会社方針で、お客さま、そして働いている社員の満足度の追求を打ち出しています。でも、それは口で言うだけじゃなくて、具体的に「実感」させないとダメだと私は思います。「満足」から、さらに「感動」へ―。学研ココファンが次の20年で目指すべきなのは、きっとそこだと確信しています。

事業本部 東日本第3事業部 東京第1ブロック長
第1号店オープニングスタッフとして、ルールを現場から作り上げていった。
「将来安泰」より、チャレンジの夢を追った

もともと、おじいちゃん子、おばあちゃん子でした。親が歯科医で忙しかったので、近所のおじいちゃん、おばあちゃん世代の人たちにかわいがられて、家で一緒にご飯を食べて、おしゃべりしながら育ってきた、そんな子どもでした。
親の跡をついで歯科医になる、と周囲から期待されることに反発していました。でも、医療系には行こうと決めていましたね。困っている人の力になりたい気持ちが強かったのだと思います。高校卒業後は専門学校で社会福祉について学びました。当時は介護保険制度がスタートして数年がたち、「超高齢化社会」という言葉も聞かれるようになった、そんな時代でした。
就職したのは2006年(平成18年)です。実は某有名病院から内定をもらっていたのですが、面接のとき、面接官とケンカしてしまって。ソーシャルワーカーのベッドコントロール(病床管理)に関して、病院上層部の、いかにも「人=お金」という話しぶりが頭にきて「それって、入院の患者様に対して失礼じゃないですか!」って言ってしまいました。
その後、ハローワークの求人で、実家の近くに、高専賃(高齢者専用賃貸住宅)と在宅介護サービスを備えた施設がオープンすること、そしてその施設がオープニングスタッフを募集していることを知りました。それが大田区南千束のココファン1号店です。ホームページをチェックしてみたら、初代所長の木村さん(現・学研ココファン取締役の木村祐介)の自撮り写真が目に飛び込んできて。所長の名前も「ゆうすけ」で私と同じだし、「ちょっと受けてみてもいいかな」と思いました。
そんなすごく軽いノリだったんですが、二次面接で小早川さん(学研ココファン代表取締役兼CEOの小早川仁)に会って。「この人、めちゃくちゃ面白いな!」と、その人柄にすっかり魅了されてしまいました。「会社をどんどん成長させて、世の中のためになる拠点をどんどん増やしていきたい」という小早川さんの言葉に、「ああ、この人の力になりたい」と心から思えました。専門学校から「将来は安泰」とお墨付きがあった某病院の内定を蹴って、ココファンに決めました。学校からは、すごく怒られましたけどね。
ただ、教育系の出版社というイメージが強い学研が、高齢者福祉事業をやっていることは全く知らなかったですね。。「えっ、学研なんだ」と気づいたのは実は入社後のことでしたから。
1号店ではオープン当初、1階でデイサービス、2階でショートステイをしていて、私はショートステイの現場でケアスタッフとして働き始めました。当時は会社も立ち上がったばかりで、今のような運営の細かいガイドラインやマニュアルはありません。なので、所長以下スタッフみんなで意見を出し合って、とりあえずなんでもやってみよう、問題があればみんなでフォローしながら変えていこう、という考え方で動いていました。まさに、さまざまなルールが日々変わっていくのを目の当たりにしていたんです。そんな無茶苦茶な状況だったので、スタッフみんながむしゃらでした。そして全員に「お客さまを一人でも多く受けよう」、そして「お客さまを大事にしよう」という強い意識がありました。
夜勤をしていると、小早川さんが夜更けにふらりと現れることもありました。差し入れを手に、「おい、元気か? サボってないか見にきたよ」って。そして、そのときに夢を語ってくれることもありました。例えば、有料老人ホームは杖のマークの地図記号があるけど高専賃の地図記号はない。「実は俺、高専賃の地図記号、作りたいんだよね」「じゃあ、やりましょうよ!」。。そんな風に経営者の夢をじかに聞いて、それを共有することができた時代でした。
現在、学研ココファンは全国で200拠点を超えますが、当時は南千束の1号店と本社の一角の小部屋だけ。社員は両方合わせても20人ちょっとで、まさに「小早川商店」でした。小早川さんをはじめ、木村さん、そして五郎丸さん(学研ココファン前社長の五郎丸徹)は、私にとって「親父」であり、「兄貴」のような存在でした。今もそれは全く変わっていません。私は、学研やココファンという会社やブランドが好き、という気持ちももちろんありますが、それよりももっと強く、ココファンの「人」が好きでたまらないのだと思います。
その人の”生きざま”を取り入れた楽しい介護

入社して20年近くなりますが、入社2、3年目の頃、デイサービスとショートステイを利用していた方で私が大好きだった、そして私のことをとても可愛がってくださった女性のご利用者さまが亡くなったときのことは、今でも特に忘れられません。
私は当時22、3歳。初めて経験する親しい人の死に、もうとてもこれ以上この仕事を続けられない、というほどのすさまじいショックを受けました。もっとあんなことをしたかった、こんなことがしたかったとベッドの上で泣き続け、今思い返すとちょっと恥ずかしいですけど、そのご利用者さまにあてた手紙を泣きながら書いていました。そして亡くなって数日後、その手紙を手にご家族の自宅にうかがいました。
ご家族の方とも親しくしていたので「実は今、仕事を辞めることを考えています」と胸の内を打ち明けました。すると、「それは許せないです」と娘さんがおっしゃったんです。「あなた、うちのおばあちゃんに『もっとこういうことしてあげたかった』って今言いましたよね。今の仕事を続けて、それを次の人にやりなさい」って。娘さんの涙ながらのその言葉にハッとしました。そうだ、その通りだと、娘さんと2人で泣きました。
今までで一番つらくて、でも、振り返ると一番うれしい出来事だったかもしれません。そのときご家族さまがそう言ってくれたから今、私がここにいるのだと思っています。私は今でも、初めて看取りを経験してショックを受けている若いスタッフには必ずこの話をするようにしています。
現場でケアスタッフとして働いていた頃の思い出は、他にもたくさんあります。ケアスタッフ時代の私の介護の特徴は、遊びのように楽しんでやること。私は人の数だけその人にあった介護の形があると思うし、介護にも、もっと楽しさを取り入れるべきだと思うんですね。例えば、お風呂が嫌いなご利用者さまがいたら、「お風呂で、水鉄砲で遊ぼう!」「スタッフに水を掛けちゃえ!」って遊びに誘うような感じでお風呂に誘っていました。沖縄出身の方には「よし、お風呂場を海にしよう」と、ビーチボールやイルカの人形を飾ったりして。それをスタッフがみんな一緒に手伝ってくれました。
デイサービスではサンタさんの恰好でクリスマスの送迎をしたり、利用者の皆さんと力を合わせてケーキを作ったり。ショートステイや住宅のご入居者さまとの外出イベントもたくさんやっていました。毎月そんな感じだったので「1号店はイベントが多すぎる」と本部から叱られたこともありました。でも、「良いアピールにはなる。ご利用者さまに「ココファンって、すごく楽しいよ!」って“宣伝”してもらえるのだから」と、そんな思いでしたね。
教科書には絶対に載らない介護もありました。介護事業をスタートさせたばかりの1号店だからこそできた、とも言えますが、根底には「ご利用者さまに楽しんでいただきたい。ご利用者さまのためになることをしたい」という強い思いがありました。こうした「ココファンらしさ」というか、ココファンの介護の「核」は今も変わらず受け継がれていると私は感じています。
「世界一」という会社の目標を共有して動く

お客さま目線で、お客さまを大事にする、という姿勢は1号店の頃から変わりません。売り上げなどの数字は、民間企業が事業継続するうえでもとても大事です。でも正直、「損得」という言葉はあまり好きではないですが、こちらがマイナスになっても、喜んで利用を続けていただけたら絶対プラスになると思っています。
お客さまとの向き合い方も「真剣」でした。お客さまに「反対意見を言うこと」はタブーかもしれません。でも、私はスタッフに「信頼関係ができていれば、自分の考えをきちんとお伝えしたほうがいい」と伝えています。責任は取るから、と。
ココファンの社内についても同じことが言えます。上から「やれ」と言われたら、基本的には、やります。ただし、私は「こうしろ」と言われたその通りには、むしろやらないことのほうが多かったですね。なんでもかんでも言われた通りにやるのではない。現場と相談して納得したうえで、その事業所に適した手法でアレンジを加えてやるのです。
今、会社は世界で一番の医療福祉企業を合言葉に目指しています。その一端を担う力になること―それが今の私の目標です。経営層の想いを共有して行動することは、とても大事なこと。1号店の頃からの私のモットーです。そして自分の役割はその「伝言役」だと思っています。
社長自身による入職者向けオリエンテーションは以前から続いていますが、最近は他にも経営層の生の声を直接聴く機会が増えてきています。会社が成長すると経営層との距離が生まれてくるのはよくある話ですが、ココファンが「距離感の近さ」を今も大切にしているということが、とても喜ばしいことだと感じています。


