スピーチロックとは?実際の具体例や気をつけるべきポイントまで紹介!
更新日時 2023/05/09
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
「スピーチロックってどういうもののことを言うの?」
「スピーチロックにならないような方法が知りたい!」
介護の現場では現在、スピーチロックに対する問題意識が高まり、研修会を行うなどの取組があります。
介護の仕事をする上で、スピーチロックについては知っておく必要があるでしょう。
そこで、この記事ではスピーチロックとは何か、スピーチロックの具体的事例、スピーチロックにあたる例文と言い換えの例など、スピーチロックについて詳しく解説していきます。
現在介護の仕事をしている方や、介護の仕事に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。
- スピーチロックは言葉がけによって身体的、精神的に行動を抑制すること
- スピーチロックは「言葉の拘束」とも呼ばれる
- 「ちょっと待って」「ダメでしょ!」などの声がけがスピーチロックになる
スピーチロック(言葉の拘束)とは
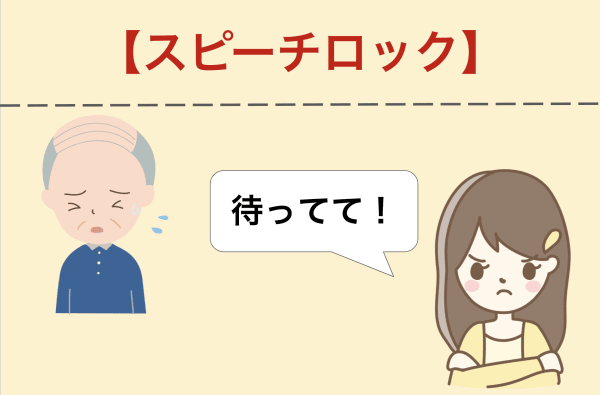
スピーチロックとは、言葉によって身体的、または精神的な行動を抑制することです。「言葉の拘束」とも呼ばれています。
介護する側が何気なく使っている言葉や声がけによって、利用者の言動が抑制されてしまうことがあります。つまり、実質的な拘束となってしまうのです。
しかし、スピーチロックには明確な線引きがありません。 一般的な声がけとの違いがわかりにくいこともあり、現在スピーチロックに対する問題意識が高まっています。
介護職員による利用者への虐待を防ごうと、最近ではスピーチロックに関する研修会、勉強会やアンケート調査が積極的に行われるようになってきました。
さまざまな介護施設で、職員に対しスピーチロックに対するアンケート調査を行い、結果を分析してスピーチロックをゼロにするための対策を行っています。
3つのロック

介護現場では、広義の身体拘束として
- フィジカルロック
- ドラッグロック
- スピーチロック
これら3つのロックが定義されています。
フィジカルロックとは、物理的に利用者の体を拘束し、動けないようにすることです。
ドラッグロックとは、薬物の過剰投与や不適切投与を行うことにより、利用者の行動を制御することを指します。
この2つは拘束具や薬といった道具がないと行えません。しかし、スピーチロックは誰でも出来てしまう恐れがある点が、他の2つのロックとは異なる点です。
スピーチロックはどんな時に起こりやすい?
介護施設ではスピーチロックが起こりやすいと言えます。例えば、人手不足の介護施設では、介護職員に余裕がなく 「ちょっと待って」 という言葉が使われることは多いでしょう。
しかし、利用者に対して「ちょっと待って」という言葉がけをすることは、スピーチロックに繋がります。
「ちょっと待って」という言葉は、なぜ待たなければならないのか、どれくらい待たなければならないのかがわからないため、利用者はひたすらその場で待つ必要があります。
また、命令口調なので、利用者に対して動かないことを命令していることになります。
そのため、利用者のの行動を抑制することになってしまうのです。スピーチロックにならないためには、利用者に対して命令口調ではなく優しい口調で、かつ具体的な内容を伝える必要があります。
具体的には、「ちょっと待って」という代わりに「今から5分ほど待っていただけますか?」や「お待たせして申し訳ありません、今からすぐにお伺いしますね」といった、時間や状況を明確に伝えることが大切です。
スピーチロックの具体的な事例
ここからは、スピーチロックの具体的な事例を上げていきます。
「ちょっと待っててください」
車椅子を使用している利用者さんが介護職員に「部屋に戻りたい」と声をかけようとしました。
しかし、職員は他の利用者さんの対応をしていたため「ちょっと待っててください」と言って去ってしまいました。
このとき、職員にとっては何気ない対応だったとしても、移動が自分ではできない利用者にとっては 「また待たなければならない」 という感情が生まれてしまいます。
また、いつまで待てばいいのかも伝えられていないため、無視されたと感じてしまうこともあります。
「~ください」という言葉遣いについても考え直した方がよいでしょう。「~ください」という言葉は一見丁寧に思えますが、これは丁寧に命令をしているだけですので注意が必要です。
「~していただけますか?」というように相手に判断を委ねる言い方だと、利用者の尊厳を守った言い方になります。
要望をうまく伝えられない場合
利用者が認知症を患っている場合、職員が要望を聞きにきたときに、上手く自分のしてほしいことを伝えられないことがあります。
このとき、職員が利用者の要望を汲み取るのではなく「何もないなら行くね」などと言ってその場から去ってしまうと危険です。
自分が意思表示をしようとしているときにそれを強制的に終わらせられてしまうと、利用者は職員に声をかけづらくなってしまい、意思表示する気持ちが抑制されてしまいます。
認知症患者は、職員に話しかけてくる内容やタイミングによって、何をしたいのか、今どのような気持ちなのか手がかりが見つかることがあります。
その点からも、認知症患者から話しかけられたときには注意して対応しなければなりません。
職員は、利用者が何を求めているのかを理解するために、言葉だけでなく利用者の表情や仕草、状況などからも情報を収集し、適切なサポートを提供するように心がけることが大切です。
スピーチロックがなぜ良くないのか
スピーチロックはなぜ良くないことなのでしょうか。スピーチロックをされると、利用者はどうなってしまうのか解説していきます。
行動意欲が減退してしまう
スピーチロックによって、自分がしたいことを禁止されたり、長時間待たされたりすると 「無視された」「拒絶された」 といったネガティブな感情が生まれます。
そうすると、利用者は意思表示することを諦めてしまったり、自分から行動するという意識が低くなってしまったりします。
その結果、行動意欲が低下してしまうのです。行動意欲が低下すると、以下で解説するようにさまざまな支障が出てしまいます。
要介護度が悪化してしまう
行動意欲が低下し自分で行動しなくなると、筋肉を動かす機会が減ってしまいます。
筋肉を動かす機会が少ない状態のままでいると、これまで出来ていたことが徐々にできなくなっていきます。
その結果ADL(日常生活の動作能力)が低下し、要介護度が悪化してしまう恐れがあるのです。
このようなことを防ぐためにも、スピーチロックにならないように一つひとつの声がけに注意し、利用者の行動を制限しないことが重要なのです。
利用者に適切な刺激を与え、運動や散歩など日常的な活動を促すことで、筋力や体力を維持・向上させることができます。
声がけに注意しつつ、職員は利用者の能力や状態に合わせた適切な活動を提供し、健康な生活を支援することが求められます。
認知症患者の場合は症状が悪化する
認知症患者は、短期記憶は低下していますが、自分の感情は強く残る傾向があります。
そのため「無視された」「拒絶された」といった感情を抱くとそれを覚えており、職員に対して「怖い」と感じるようになります。
そのことが被害妄想やせん妄に繋がっていく恐れがあるため、注意しなければなりません。
また、徘徊がある場合、本人は目的があって行動していたのに「座っていて」とだけ言われてしまうと「なぜ座っていなければならないの?」という感情になります。
このような結果、認知症の方はストレスを感じるようになり、症状がエスカレートしてしまうこともあるため注意が必要です。
職員は、利用者の気持ちに寄り添い、適切なコミュニケーションを取りながら、利用者の能力や状態に合わせたサポートを提供することが大切です。
利用者が抱える不安や疑問に対して、優しく丁寧に対応することで、利用者との信頼関係を築くことができ、症状の軽減につながることもあります。
人と人とのコミュニケーションにおいての問題
スピーチロックは身体拘束という面で問題ではありますが、そもそもスピーチロックになってしまう言葉がけ自体はコミュニケーションの一環で行われます。
人手不足の介護施設では、職員に余裕がなく強い言葉で伝えてしまうこともありますが、相手が認知症患者や高齢者であったとしても、一人の人間として尊重する気持ちが大切です。
利用者を尊重する気持ちが欠けているため、声がけがスピーチロックになってしまうとも言えます。利用者に対して丁寧なコミュニケーションを取り、相手の立場に立って思いやりを持って接することが、スピーチロックを防止するために必要なことです。
職員は、常に利用者の視点に立ち、適切な声がけやサポートを提供することで、利用者の生活の質を向上させることが求められます。
スピーチロックの対策方法の取組は?
スピーチロックをしないためには、どのような対策方法を取ればよいのでしょうか。
無意識にスピーチロックをしている可能性もある
職員が忙しくてすぐに対応できないとき、普通に伝えたつもりでも余裕のない強い言い回しや命令口調になってしまい、無意識のうちにスピーチロックになっていることがあります。
例えば「あとで来るから」と言って、いつまで待てばよいのかわからない状態で利用者を待たせることは、行動の拘束に繋がります。
また、高齢者は転倒をすると大怪我に繋がるため、安全のためを思うあまり「一人でやらないで」とつい厳しい言い方になってしまうこともあるでしょう。
このような言い方はしてしまいがちですが、強い口調で利用者の行動をやめさせると利用者の心理面にストレスを与え、精神的な拘束になってしまいます。
また、これは稀な例ですが、職員が利用者よりも上の立場であると思い込み「虐待ではなく躾」としてスピーチロックを行っていることもあります。
このように、無意識の状態でスピーチロックをしてしまうこともあるため、普段からスピーチロックをしないように細心の注意を払うことが必要です。
否定形ではなく、依頼形で伝える
「~しないで!」といった否定形の言葉は、どうしても強い口調になりがちです。
利用者に話しかけるときには 「~していただけますか?」 といった、依頼形を使うようにしましょう。
依頼の形であれば、利用者を尊重しながらも自分の要望を伝えることができます。
ただ「~してくれる?」といった、依頼形ではあっても敬語を使わない言い方も、利用者に対する敬意が欠けているため問題です。
尊敬語・謙譲語を使い、利用者に対して常に敬意を持った言い方で接するようにしましょう。
このように、伝える内容は同じでも言い方に気を付けることでスピーチロックを回避することができます。
スピーチロックを防ぐ言い換え言葉
スピーチロックを防ぐためには、言い換える言葉の一覧表を作成し、職員間で共有しておくのがよいでしょう。
言い換えの例としては「ちょっと待って」→「~しましたらすぐに伺いますのでお待ちください」などがあります。
後ほど、言い換えの例をいくつかご紹介しますので、常に言い換えの方の言葉を使うよう意識しましょう。
また、言葉遣いだけではなく、表情が無表情にならないよう、笑顔で話すことも大切です。
相手の立場を考えることが大切
声がけは、利用者に対して話かけるという行為であるだけではなく、「応対」「おもてなし」の意味がある接遇の面も合わせて持っています。
利用者に認知症があったとしても、思いやりを持ち一人の人間としてコミュニケーションを取ろうとする姿勢が大切です。
現在、介護業界では、利用者に対して子供に話しかけるような言葉遣いをすることはやめ、接遇マナーを守って接することが重要になっています。
「だめ!」などの否定形は強い印象になりがちです。また、子供への注意のような言い方なので、利用者や家族が不快に感じることもあります。
依頼形などの柔らかい言葉で丁寧に、かつ具体的に気持ちを伝えるようにしましょう。
また、ただ自分の要望を伝えるだけではなく、利用者の話を最大限聞くことも大切です。
言い換え言葉の例文集
スピーチロックにならない言葉への言い換え例について、日頃から同僚などと勉強会をしたり、研修をしたりして、職場全体で共有しておくことをおすすめします。
ここでは、言い換えの例文をご紹介します。
| スピーチロックになる声がけ | 言い換え例 |
|---|---|
| ダメでしょ やめて |
「○○さん、どうされましたか?」 「それは危ないので、他のことをしましょう」 |
| 早くして | 「急がなくても大丈夫ですよ」 |
| さっきも言ったじゃない | 何度も根気よく、笑顔で伝える |
| そこにいて | 「どこに行かれるんですか?」 「一緒に行きますので、あと○分待っていただけますか?」 |
| 座って | 「立っていると危ないので、座っていただけますか?」 |
これが適切な言い換えの全てではありません。効果的な言い換えは他にもたくさんあるでしょう。
言い換え一覧表を作成しておき、新しい言い換えを思いついたら表に随時追加して、言い換えをたくさん考えておくことをおすすめします。
スピーチロックについてまとめ
- スピーチロックは介護施設で起こりやすい
- 日頃からスピーチロックを言い換える例文を集めておき、職場で共有するのがよい
- スピーチロックを防ぐためには、否定形ではなく依頼形で言い換えるのがよい
介護業界は人手不足であることから、つい利用者に対して簡単な声がけで済ませてしまうこともあります。
しかし、それがスピーチロックとなり、利用者を拘束してしまうことに繋がります。
とっさのときでも丁寧に接することができるよう、普段から言い換えの例文を考えておくことをおすすめします。
常に利用者の方々に思いやりを持って接することができるよう、スピーチロックゼロを目指していきましょう。
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。
監修した専門家の所属はこちら









