回想法とは|認知症に対するリハビリ効果や注意点・実践方法についても解説
更新日時 2023/12/22
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
「回想法って、認知症にどんなリハビリ効果があるの?」
「回想法ってどうやればいいのか知りたい!」
認知症のリハビリ療法はさまざまありますが、その一つに回想法があります。この記事では、実践方法、効果、注意点など、回想法について詳しくお伝えします。
認知症のリハビリについて知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください!
- 回想法とは、認知症の人が自分の過去や昔のことを話す療法
- 自分の過去や昔の話を話すことで、精神や認知機能に安定をもたらす効果が期待できる
- 実践する際の注意点としては、「話し手のプライバシーを守る」などがある
回想法とは

回想法とはアメリカで生まれた心理療法です。回想法とは精神科医のロバート・バトラー氏が1960年代に確立した療法で、グループを組み、グループのメンバーに対し「自分の過去を話す」ことを行います。
そのことにより、精神的な安定感が得られ、認知機能にもよい影響を与えるとされています。
回想法は、日本でもうつ病の高齢者に対して行っていましたが、
現在は認知症の症状に対する、薬を使わない療法として活用されています。
昔を思いだし自己を再確認
回想法で自分の過去を話すにあたって、過去の自分の写真や思い出の品物などを見直すことになります。
そうすることにより、過去の記憶をより鮮明に思い出すことができるため、自分自身について思い直す機会ができます。
認知症の特徴として 「昔の記憶は忘れていない」 点がありますので、回想法は認知症に効果的とされています。
過去の自分を思い出すことにより、自分の存在意義を再認識できたり、大勢の前で自分の話をすることによってグループのメンバーに対して仲間意識が芽生えたりするため、回想法は認知症に対する療法として使われているのです。
回想法で得られる効果
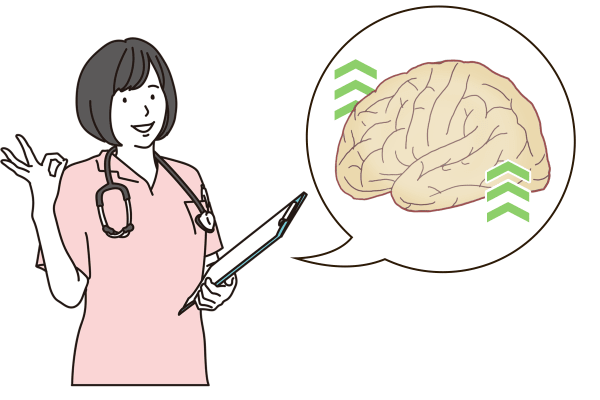
ここからは、回想法により、どのような効果が得られるのか、具体例を紹介していきます。
先ほど、過去の自分を思い出すことにより、自分の存在意義を再認識できるという効果があると述べました。
認知症の症状により、上手く日常生活が送れず自信を失っている方でも、昔の自分を思い出すことによって、楽しい気持ちになり、自分に対する自信が少しずつ戻ってきます。
そのため、回想法を何回も経験することにより、だんだん明るくなってくる患者さんも少なくありません。
人間関係の改善
ここまで、回想法が認知症に与える影響についての研究をご紹介しましたが、回想法は、認知症の療法として確立されているわけではありません。
しかし、回想法で自分の話を聞いてもらうことにより孤独感がなくなったり、安心感が生まれたりするため、コミュニケーションの改善が期待できます。
回想法を通じて認知症の方々が過去の思い出を共有することで、家族やケアスタッフとの絆を深め、より充実した日々を送ることが期待されます。
認知症の症状によってはトラブルが起きがちですが、上記のようにコミュニケーションの面で改善されれば、トラブルが減り、人間関係が改善すると考えられます。
気持ちが穏やかに
認知症になると、どうしても家に閉じこもりがちになってしまいます。また、家族やヘルパーなどとの意思疎通がうまくできず、歯がゆくなり孤独感を抱いてしまうこともあるでしょう。
しかし、回想法により人に対して自分の過去を話すことで、自分の話を誰かに聞いてもらう経験ができます。 そのことにより、孤独感が薄れていき、気持ちが穏やかになって行くのです。
認知症のリハビリ療法に
国立長寿医療センターの研究によると、回想法を行っている高齢者は、過去の話をしたり、思い出の品を見たりすると脳の血流が増えることがわかりました。
回想法を認知症の療法として続けていくことで、認知症の認知機能の障害である中核症状が改善したという研究もあります。
回想法は、認知症の症状にも効果があると期待されているのです。
認知症の方向けの施設はこちら!回想法を行うための準備

回想法を始める前には、しっかりと準備をしておくことが大切です。まず最初に行うことは、患者さん本人が回想法ができる状態か確認することです。
例えば、人と話すコミュニケーション能力があるか、集団の中にいられるかどうか、人の話を聞ける聴力があるかなどをスタッフ側がチェックしておく必要があります。
なお、大勢の人の前で話すのが苦手な患者さんに対しては、一対一の回想法をするなど、患者さんそれぞれの性格にあった準備を行いましょう。
話を聞く側としても、話し手と同じような年代で、昔の話をされたときに理解できる方をメンバーにすることが望ましいでしょう。
用意しておくべきもの
昔のことを思い出しやすくするため、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚といった五感に訴えかけられるものを用意しましょう。
例えば、昔の写真、音楽、本、新聞、映像、地図、おもちゃ、生活用品、着物、季節の花、地域の特産物、季節の行事に関するもの、香りがするものなどがよいでしょう。
また、ただこれらの品物を準備しておくだけではなく、あらかじめ部屋に飾っておき、患者さん本人に見える場所に置いておくことが大切です。
参加者の相性などで調整
回想法は、グループで行うものと一対一で行うものがあります。グループで行う際は、参加するメンバーの相性について配慮しておく必要があります。
毎回参加者からアンケートを取るなどして、このメンバーで回想法を継続しても問題ないか、逐一チェックすることも重要です。
グループで行う回想法は、リーダー役のスタッフが1人とサブリーダー役のスタッフが1人、そして参加者は6~8人の、合計8~10人で行うのがおすすめです。
回想法を実践する方法
回想法には、一対一で行う個人回想法と、10人前後で行うグループ回想法があります。それぞれの方法について解説します。
個人回想法
個人回想法には、特定の話題について一対一で話す方法の他、日常会話をする中で過去を思い出し、自分について語るといった方法もあります。
また、居宅介護サービスを受けている方に対し、ヘルパーが話しかけ昔の話を聞くことも個人回想法になります。
話の聞き手は、必ずしも医療従事者や福祉・介護のスタッフでなくとも可能です。
自宅にある、昔の映像や音楽などを材料とし、家族が昔の話を聞くことでも個人回想法になります。
グループ回想法
グループ回想法は、先ほど述べたとおり、リーダー・サブリーダーのスタッフ2名と、6~8人の参加者で行います。時間は1時間で、8~10回をひとまとまりとします。
まず、スタッフ側が事前準備として参加者の生育歴などから触れてはいけない話題を調べ、全員が楽しく気軽に話せる話題を決めます。
また、スタッフはあくまでも傾聴する立場であり、回想法を実施することへのスキルも必要です。スタッフは、積極的に研修を受ける姿勢が求められます。
回想法の効果を最大限に引き出し、参加者の感情や思い出に寄り添いながらサポートするためには、スタッフ自身が継続的な学びと成長を追求することが重要です。

 老人ホーム・介護施設を探す
老人ホーム・介護施設を探す
回想法を実践する際の注意点

この見出しでは、回想法をより効果的なものにするためのコツをご紹介します。
他の人に話さない
回想法で話される内容は、話し手のプライバシー情報が含まれているため、話された内容は決して他の場で話してはいけません。
特にグループでの回想法では、プライバシー保護に細心の注意を払う必要があります。
聞いた話を参加者が他の場所で話してしまうと、噂話として個人情報を含むプライバシー情報が広まってしまう恐れがあるからです。
参加者やスタッフは、回想法の実施において個人情報の取り扱いについて明確なルールを守ることが求められます。
ただし、今後の介護のために役立てたい場合は、話し手本人に許可を得れば情報をスタッフと家族間で情報共有することは可能です。
無理に思い出させない
人は誰でも話したくない話題があります。また、何とか話せる話題でもストレスを感じることもあります。
そのため、スタッフは回想法を行う前に、参加者が話したくない、隠したいなど、ネガティブに思っている話題を調べておくことは必須です。
また、心理療法全般に言えることですが、楽しく過ごせたとしても心身への疲れは出てしまいます。
特に認知症の方は脳の疲れが出やすいですので、スタッフは参加者をよく観察し、疲れてきていると感じたら無理やり話を続けさせず、その場は終わるようにしましょう。
話を否定・訂正しない
話し手が話す中で、事実とは異なる内容が話されることもあります。しかし、訂正はしてはいけません。
回想法は、正しく過去を思い出すことが目的ではなく、 安心感を抱いたりコミュニケーションを楽しめたり、自信を持てるようになれたりすることが目的です。
他の参加者が話を訂正しようとすることもありますが、話し手本人の尊厳を守れるよう、スタッフがグループを誘導して、話し手の語ることにグループ全体で耳を傾けるようにすることが大切です。
最後はポジティブな話題に
回想法を行っていると、ときには辛い思い出を話す方もいます。どの心理療法でもどのように療法を終えるか(クロージング)が重要ですが、回想法でも終わり方には注意を払うことが大切です。
その方が辛い思い出を話して話を終わりにすると、その後の日常生活にまで辛い思い出が影響してしまいます。 そのため、最後はポジティブな話題で終わることが重要です。
また、療法が終わったあとは明るい音楽をかけたり、参加者におやつを配ったりするなど、楽しい雰囲気で終わることも心がけましょう。
これにより、参加者は回想法のセッションが終わっても穏やかで満足感のある気持ちで帰ることができ、回想法のポジティブな効果をより持続させることができます。
自宅で行う際の注意点
自宅で回想法を行う際にはいくつか注意点があります。例えば、回想法を行う場所です。
新しい家具や家電がある部屋で行うと、昔の話をしていても、その家具や家電を目にしたことをきっかけに、現在の話に移ってしまうことがあります。
そのため、過去のものが多く置いてある部屋や、落ち着いて話せる部屋で行うことがおすすめです。
また、聞き手が家族であることも、注意すべき点の一つです。家族に対し話している中では、自然にその家族に対する説教に話が移ってしまうことがあります。
しかし、回想法では話の内容は否定せず、傾聴することが重要です。我慢して傾聴に徹することができる人が聞き手になる必要があります。
自宅にはアルバム、旅行のお土産、家族の集合写真など過去の話をするきっかけになるものがたくさんあるので、話のきっかけが多様になることが期待できます。
【専門家監修】認知症による暴言・暴力の対応方法|原因や改善する方法についても解説

家族の介護のストレスを軽減するには?認知症介護のポイントやイライラの対処法を紹介

介護施設で行う際の注意点
介護施設でグループ制の回想法を行う場合は、話し手の情報が利用者の方々に広まらないよう特に配慮が必要です。
介護施設でプライバシーに関わる話が広まってしまうと、話し手の方の尊厳にかかわることはもちろん、その方がその施設に居づらくなってしまいます。
スタッフ側は、話し手がプライバシーに関わる話をし出したらうまく別の話に誘導するなどの配慮をし、ご本人の尊厳を守りましょう。
また、スタッフ間でもお互いに注意し合わなければならないことがあります。「高齢者は全員昔の歌で盛り上がるだろう」などの高齢者に対する偏見があり、回想法で実施するテーマを間違える可能性があるからです。
参加者を「高齢者」とひとくくりにせず、それぞれの方の好みや生活などから適切な話題を見つけるスキルが必要です。
回想法に関する資格・研修
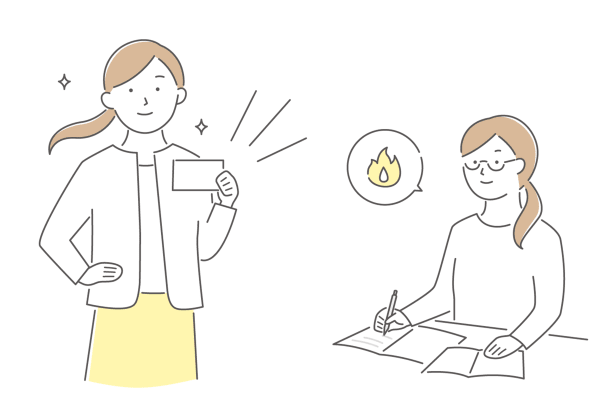
回想法を勉強したい方のために、いくつか資格がありますのでご紹介します。
認知症ライフパートナー
認知症ライフパートナーは3級~1級まであります。認知症ライフパートナーは、認知症の方の尊厳を大切にし、今後もその方らしく生きていけるように支援する資格です。
そのためには、その方の好きなスポーツや好きな曲などを活用して、脳の活性化をはかると効果が期待できます。
ただ、認知症の方がご自分の好きなものを伝えることが難しい場合は、その方の表情や反応などからその方を理解するスキルが必要となります。
このような専門的スキルを得るため、認知症ライフパートナー資格が設けられています。
認知症ライフパートナー3級と2級は受験資格がなく、誰でも受験できます。 検定試験の公式テキストが発売されているので、3級と2級の場合はそれで勉強すれば合格が可能です。
1級は2級合格者のみが受験できます。なお、1級の出題範囲は公式テキストだけではないため、難易度が高いと言えます。
パーミングセラピスト
「パーム」とは英語で「手の平」のことであり、「パーミング」とは手の平を使ったコミュニケーション技術で、回想療法の一つです。会話をする機能が下がっている方へ行います。
パーミングセラピストは手をマッサージしながら患者さんに言葉かけをし、患者さんに過去のご自分の話や懐かしい思い出などを語っていただきます。
資格を取得するには、通信講座でDVDを見ながらスキルを習得したり、レポートを提出したりします。取得できる期間はおよそ半年ほどです。
熟練したパーミングセラピストは、手のぬくもりや言葉を通じて患者さんとの絆を深め、回想療法の効果を最大限に引き出すことができます。
心療回想士
心理回想士はレミニシャンとも呼ばれます。心療回想法では、話し手をレミニンと呼ぶため、聞き手である心理回想士はレミニシャンと呼ばれるわけです。
心理回想法では、事前に決められている内容を心理回想士がインタビューし、話し手が答えます。 これを繰り返すことでコミュニケーションが深まります。
心理回想士になるには、まず通信講座で回想療法を学び、心理回想士5級を取得します。 その後、4級以上になるために研修や研究会に参加し学ぶことで昇給できるシステムです。
認知症の方向けの施設はこちら!回想法についてまとめ
- 回想法を実践することで、脳の血流量が多くなるとの研究もあり、認知症の進行を抑制するリハビリとして期待されている
- 回想法を実践するには、昔のことを思い出しやすくするため、昔の写真、音楽、新聞、おもちゃ、生活用品などを準備するとよい
- 回想法の注意点として、クロージング(終わり)はポジティブな内容で終わることも重要
回想法は、認知症の方が自分の過去や昔の話をすることによって「自分の話を聞いてもらえる」「共感してもらえる」といった実感を得て、安心感や自信を取り戻す療法です。
しかし、ただ認知症の方に話してもらえばよいわけではなく、グループの場合は実践するスタッフ、個人で行う場合は家族やヘルパーなどに専門的なスキルがないと、効果的な療法になりません。
回想法に興味がある方は、今回ご紹介した資格を取得して、専門的な知識やスキルを得てみてはいかがでしょうか。
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。
監修した専門家の所属はこちら









