地域密着型サービスとは|各種類のサービスや対象者の特徴まで徹底解説!
更新日時 2023/12/29
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
「地域密着型サービスとは何なの?」
「地域密着型サービスにはどのような種類があるの?」
このような疑問をお持ちの方、いらっしゃいませんか?
地域密着型サービスとは介護保険制度に含まれるサービスで、認知症患者や高齢者が住み慣れた地域で生活できるようにサポートする仕組みです。
地域密着型通所介護や認知症対応型通所介護などの種類があるので、必要に応じて利用するサービスを決めましょう。
また、介護を受けるためには適切なサービスでなければ意味が無いので、サービス内容について疑問があれば担当窓口に相談することが重要です。
こちらの記事では、地域密着型サービスの種類やサービス内容、また今後の課題などを詳しく解説していきます!
- 認知症や高齢者が、希望する地域で生活できるように支援する仕組み
- 対象者は、指定を受けた市町村に住んでいる要介護認定を受けている人に限られる
- 通所サービスや訪問サービス、施設サービスなど豊富な種類がある
- 自分のニーズに合ったサービスを利用しないと意味が無い
【イラストで意味を解説】地域密着型サービスとは

地域密着型サービスとは、認知症を患っている高齢者や中重度の要介護高齢者等が、住み慣れた地域で生活できるように支援するサービスです。
2006年4月の介護保険制度改正により創設され、市町村が指定した事業者が住民に様々なサービスを提供しています。
指定した市町村の被保険者のみがサービスを利用でき、また事務所は地域住民と交流が持てるような場所にあるのが特徴です。
地域密着型サービスは、地域のボランティアや地域の医療機関と連携しながら、高齢者や要介護者の生活支援を行うことも特徴とされています。
施設規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細かく応えることができると期待されており、住み慣れた地域で暮らしたいと考えている人たちにとってはありがたいサービスと言えるでしょう。
なお、提供されているサービス内容は各市町村によって異なるので、詳細はケアマネジャーや地域包括支援センター、役所の窓口に問い合わましょう。
対象者
地域密着型サービスの介護給付を受けることができる対象者は、指定を受けた市町村に住んでいる要介護認定を受けている人です。
地域密着型サービスにはいくつか種類がありますが、介護予防を目的とした「地域密着型介護予防サービス」は要支援の認定を受けている住民を対象しています。
自宅や地域での生活支援を受けながら、認知症や要介護のリスクを予防するためのサービスを利用することができます。
なお、「地域密着型介護予防サービス」のサービス内容は
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」
となっています。
居宅介護サービスとの違いは?
居宅介護サービスを利用する場合、訪問介護・訪問介護を利用する人が一般的です。
訪問介護・訪問介護と地域密着サービスとの違いは、特に「同一事業者からサービスを提供してもらえるか」にあります。
また、訪問介護・訪問介護は住んでいる市町村に縛りが無いのに対して、地域密着型サービスは市町村の被保険者のみがサービスを利用できます。
訪問介護・訪問介護では、自宅で個別のケアやサポートを受けることができるため、プライバシーや自立した生活を重視する方に適したサービスと言えます。
地域密着型サービスであれば、同一事業者を指定できるのでアットホームな雰囲気で自分のニーズに近いサービスを受けられる安心感があります。
どちらのサービスが自分に向いているのかを吟味した上で、利用を検討しましょう。
地域密着型介護予防サービスとは?
地域密着型サービスの中の地域密着型介護予防サービスは、要介護状態になってしまうのを予防する役割があります。
地域密着型介護予防サービスは要支援1~2の人が受けることができ、住み慣れた地域を離れることなく生活できるように、地域の特性を生かしながら柔軟なサービスを提供してくれます。
地域密着型介護サービスの予防版なので、原則として指定した市町村に居住する被保険者のみ利用可能です。
地域密着型サービスの種類【1.通所サービス(デイサービス)】

それでは、地域密着型サービスの一つである通所サービス(デイサービス)について紹介していきます。
なお、以下のトピックは介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」を参考にしています。
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護は、定員18人以下の小規模デイサービスです。
小規模なのできめ細かいサービスの提供が可能となっており、入浴や食事などの介護支援や機能訓練、レクリエーションを楽しむ時間が充実しています。
利用者の日常生活のサポートだけでなく、地域のイベントや交流活動への参加などのサービスも提供されています。
また、地域密着型通所介護は日帰りで利用できるサービスも提供しているので、家族が日中仕事に行っている間に利用するケースが多いです。
ただし、要支援1・2の人は利用できませんので、注意しましょう。
小規模デイサービス(地域密着型通所介護)とは|サービス内容や料金・利用条件も解説
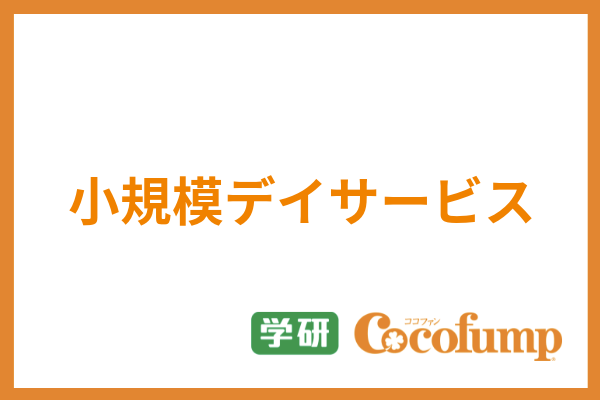
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は認知症の方の対応に限定した介護サービスで、食事や入浴などの生活介助、機能訓練を日帰りで利用できます。
それぞれの利用者に対して専門的なケアやコミュニケーション支援を行い、心身の状態に合わせた個別の支援プランを提供しています。
一般の通所介護(デイサービス)では認知症罹患者に対応していないことが多い上に、本人が施設の雰囲気に馴染めないケースもあります。
しかし、認知症を発症している方や発症の予兆が見られる方へのサービスに限定しているので、安心して利用できると評判です。
なお、サービスは以下の3種類です。
- 併設型:特別養護老人ホーム等に併設
- 単独型:認知症対応型デイサービスとして単独で設置されている
- 共用型:グループホームのリビングや食堂の共用スペースで提供
以上の中から、自分のニーズに最も合うものを選んでください。
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)とは?対象者や定員・利用条件も紹介

療養通所介護
療養通所介護は、医療ケアを必要としている人を対象にした介護や機能訓練を実施するデイサービスです。
療養に関するサービスも提供しているので、送迎サービスが付いている上に車中でも看護師が付き添ってくれます。
医療依存度が高く、一般的なデイサービスの利用が難しい人に多く利用されており、こちらも多くの介護者・被介護者を助ける存在と言えるでしょう。
なお、利用対象者は要介護1以上で、常に看護師による観察を必要とする難病罹患者や重度要介護者、がん末期患者です。
不定期な利用も可能なので、利用者にとっては非常にありがたいサービスと言えるでしょう。
地域密着型サービスの種類【2.訪問サービス】
続いて、地域密着型サービスの中の訪問サービスについて紹介していきます。
介護のプロが自宅に訪問してくれるので、こちらもありがたいサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問看護介護
定期巡回・随時対応型訪問看護介護は、時間帯を問わず1日複数回の定期訪問と随時の対応が必要な人に対して行われるサービスです。
介護・看護が密接に連携しながら各人にとって必要なサービスが提供されるので、家族の介護負担を減らしてくれるでしょう。
具体的なサービスを見てみると、ホームヘルパーや看護師などが定期的に自宅を訪問し、食事や排泄などの生活介助や必要な療養上の世話を行います。
また、急な体調不良やトラブルがあった際には随時対応を受けることができ、利用者の状況に応じた訪問介護や訪問看護も受けることができます。
24時間体制で対応してくれるので、利用者本人に万が一のことが起きても安心です。
なお、要支援1~2の人は利用することができません。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは|サービス内容・費用から事業所の選び方まで解説

夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護には、「定期巡回」と「随時対応」の2種類があります。
どちらも、万が一の際に対応しづらい夜間帯でも訪問介護を行ってくれる、非常に頼もしいサービスです。
定期巡回を利用すると、18時から翌朝8時までの夜間帯にホームヘルパーや看護師などの訪問を受けて、排泄介助や安否確認等のサービスが受けられます。
随時対応を利用すると、急な体調不良や転倒などの事故に遭遇した場合などにホームヘルパーを呼んで介助を受けることが可能です。
地域密着型サービスの種類【3.施設サービス】
次に、地域密着型サービスの施設サービスについて紹介していきます。
施設においても有意義なサービスを受けられるので、内容を詳細に把握しておきましょう。
認知症対応型共同生活介護【グループホーム】
グループホームとも呼ばれている認知症対応型共同生活介護は、認知症の高齢者が共同で生活する住居で、少しでも自立した生活を送るための施設です。
食事や入浴などの生活介助などの介護や支援、機能訓練を受けることができます。
一般的に少人数制で、それぞれの能力を活かしながら家庭的な雰囲気の中で生活を送ることができるので、ストレスなく日々の生活を楽しめる点がグループホームの魅力です。
【イラストで解説】グループホームとは|サービス内容・特徴から費用・入所条件まで解説
 近くのグループホームを探してみる!
近くのグループホームを探してみる!
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護では、入居定員30人未満の小規模な介護施設で介護サービスを受けることができます。
有料老人ホームや軽費老人ホームなどにおいて、食事や入浴などの生活介助をはじめとした介護、また機能訓練を利用することができます。
なお、要支援の人は利用することができないので注意しましょう。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、要介護者を対象としているサービスで、サービス内容は特別養護老人ホームと似ています。
定員30人未満の小規模な特別養護老人ホームで、入浴・排せつ・食事等の介護だけでなく、利用者に合わせた機能訓練を利用できます。
介護に精通したエキスパートから質の高いサービスを受けられる点が魅力です。
地域密着型サービスの種類【4.複合サービス】
続いて、地域密着型サービスの複合サービスについて見ていきましょう。
小規模多機能居宅介護
小規模多機能居宅介護とは、介護度が中重度となっても暮らし慣れた在宅での生活をできる限り継続できるように支援する、小規模な居住系サービスです。
1つの事業者と契約すると、通いを中心としながら「訪問、短期間の宿泊」などを組み合わせたサービスを利用することができます。
つまり、複数のサービスを利用するために複数の手続きをする必要はないので、手間がかからない点が魅力です。
また、一つの事業者と契約すれば様々なサービスを利用できるため、顔なじみのスタッフができ、利用を重ねる度に安心感が得られるでしょう。
特に、新しい環境やスタッフの変化にうまくなじめない人におすすめのサービスです。
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) は、小規模多機能居宅介護と似ています。
一つの事業者と契約するだけで、通いを中心として「宿泊」や「訪問介護・訪問看護」などのサービスが利用できるになる複合型な介護サービスです。
小規模多機能型居宅介護に訪問看護がプラスされている点が特徴で、これにより医療的なニーズのある高齢者も利用しやすくなっています。
医療的ケアがあった方が安心できる人などは、利用を検討すると良いでしょう。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)とは|利用条件や費用まで全て紹介
 看護小規模多機能型居宅介護の事業所を探す!
看護小規模多機能型居宅介護の事業所を探す!
地域密着型サービスのメリットとは
地域密着型サービスを利用するメリットは、大きく分けて3つ挙げられます。
こちらのトピックでは、地域密着型サービスを利用するメリットを紹介していくので、参考にしてください。
利用時間や回数を柔軟に指定できる
地域密着型サービスは、小規模な施設を気軽に利用できたり、短い滞在時間で多くの回数を利用できる強みがあります。
つまり、利用者のニーズにきめ細かく応えられる点や柔軟にサービスが設計されている点が大きなメリットと言えるでしょう。
また、サービスの基準や介護報酬なども地域の実情に合わせて市区町村が決めているので、比較的柔軟に対応してくれる傾向にあります。
施設に入居するよりも費用を抑えられるので、経済的な不安も小さいです。
介護保険適用で信頼できるサービスを選べる
地域密着型サービスは小規模な施設が中心なので、顔なじみのスタッフから介護サービスを受けられます。
つまり、大きな安心感を持ってサービスを受けることができる点が大きなメリットと言えるでしょう。
一方で、訪問介護サービスであれば介護度が重度になればなるほど複数の介護事業者が絡み、介護事業所ごとに介護職員が違うので知らないスタッフと顔を合わせる機会が多いです。
しかし、地域密着型サービスは一つの事業者から複数のサービスを受けられるため、顔なじみのスタッフを作りやすいのです。
また、介護保険が適用された金額でサービスを受けられるので、利用者だけでなく家族としても安心して利用できるでしょう。
小規模でアットホームな傾向
地域密着型サービスは小規模運営のサービスが中心なので、スタッフだけでなく利用者同士でもコミュニティを作りやすいです。
スタッフと利用者同士も顔なじみになりやすいと、自然とアットホームな雰囲気になるため、気軽に利用しやすい点が大きなメリットと言えるでしょう。
人見知りな人や団体行動が苦手な人、また認知症の人であれば小規模の事業所を利用すると良いでしょう。
地域密着型サービスの今後の課題
地域密着型サービスは、在宅介護などでは手の届かないきめ細かいサービスを受けられる点が魅力です。
高いニーズと期待が持たれていましたが、制度が作られてから事業所・利用者共に数は思ったほど増えていないのが現状です。
こちらのトピックでは、地域密着型サービスの課題について見ていきましょう。
【事業者側の課題】低い採算性と人手不足
事業者側から見ると、定員が少なかったり介護報酬が低いなどの理由で、採算が取れない点がデメリットです。
採算が取れないと事業として運営するのが難しいので、これはやむを得ないと言えるでしょう。
実際、地域密着型サービスはサービス内容や時間帯の対応範囲が広く、それを網羅するための人材確保が難しいのは事実です。
利用定員が少ないとはいえ、小規模事業所だと少ない人数で運営するケースが多く、一人あたりのスタッフの負担が大きくなってしまうのです。
【事業者側の課題】ケアマネージャー間での認知度の低さ
そもそも、地域密着型サービスの認知度がケアマネージャー間でもそこまで高くありません。
つまり、ケアプランなどを通して適切な介護サービスを提案するケアマネージャーが施設について知らないので、サービスの利用者が増加しないのも当然でしょう。
また、地域密着型サービスを利用することで、担当のケアマネージャーが変わってしまう点も、現在のサービス制度における問題点です。
そのため、施設関係者とケアマネージャーが円滑に情報共有できるシステムを構築し、利用者に伝えるシステムが必須と言えるでしょう。
【利用者側の課題】前任のケアマネージャーを頼れない
地域密着型サービスを利用すると、小規模多機能型居宅介護に所属しているケアマネジャーがケアプランを作成することになります。
つまり、前任ケアマネージャーとの関係が切れてしまうことがあるので、この点を不安に感じる方は多いです。
また、定員が設けられていることから、希望するサービスを受けられない可能性もある点もネックです。
利用者側にもこのような心理的ハードルがある点も、今後の課題と言えるでしょう。
介護費用についても要検討
地域密着型サービスを利用する際の費用についても確認しておきましょう。
介護保険は、主に在宅で受ける「居宅サービス」と公的施設に入居する「施設サービス」、夜間の訪問介護などに対応してくれる「地域密着型サービス」の3つに大別されます。
介護保険の受給者の内、居宅サービスを受ける人の割合は約70% で、具体的な居宅サービスの内容を見てみると、ホームヘルパーが在宅で生活介助をしてくれる訪問介護、施設に通って介護を受けるデイサービスなどが挙げられます。
地域密着型サービスは在宅介護より高い
厚生労働省の調査によると、訪問介護を利用する場合の1人当たり給付額は2018年度で月平均6万7000円で、自己負担金額に換算すると月平均約7000~2万9000円という結果でした。
一方で、施設サービスはは居宅サービスを利用するケースと比較すると費用負担は高くなりがちです。
入居して施設サービスを受ける場合、要介護度や高額介護サービス費の適用によって差がありますが、自己負担額の月平均額は2万8000~10万8000円となっています。
地域密着型サービスはこれらの中間くらいのイメージで、自己負担の月平均額は15,000~70,000円程度となっています。
介護をする上で、本人が快適に過ごせるように配慮することは非常に重要ですが、満足するサービスをすべて利用しようとすると予算が青天井になってしまいます。
資金が枯渇してくると介護サービスを絞らざるを得なくなり、また資金的な不安が常に付きまとうようになってしまうので、介護保険の限度額を意識しつつ必要なサービスを吟味しましょう。
介護保険制度の理解なども重要
40歳以上になると介護保険料を払うことになりますが、保険料を払っていても、実際に介護が必要となるまで制度内容について十分に理解できていないケースは非常に多いです。
各自治体の介護関係担当窓口で、介護保険の仕組みやサービス内容について説明されている冊子や資料が置いてあるので、こちらを活用して情報を集めるといいでしょう。
これらの資料は、無料で入手できる上に有益な情報が満載です。
地域包括支援センターの所在地や連絡先についても載っているので、手元に置いておくと安心できるでしょう。
また、親が元気な内にかかりつけ医やどのような介護を望んでいるのかを把握し、在宅介護か施設入居か、あるいは地域密着型サービスを利用するのか話し合っておくと安心です。
ケアマネジャーとのコミュニケーションは積極的に
一般の方で、介護保険制度や介護サービスについて精通している人は多くありません。
ケアマネジャーはケアプランを作成してくれる介護の専門家なので、介護に関する専門家なのでケアプランをそのまま受け入れがちです。
しかし、作成してくれたケアプランがニーズに合致しているとは限らないので、積極的に求めていることをケアマネジャーに伝えることが重要です。
介護のニーズのミスマッチが起きてしまうと、要介護者も家族も漠然と不安や不満を抱えたままサービスを受けることになります。
生活の満足度が落ちてしまうとサービスを利用する意味が無いので、しっかりと求めているサービスについて主張することが重要です。
地域密着型サービスを利用する場合であっても、しっかりと家庭の都合や介護のニーズを伝えて積極的にコミュニケーションを取りましょう。
地域密着型サービスまとめ
- 住み慣れた地域で暮らしたい人にとって、魅力的なサービス
- 利用時間や利用回数を柔軟に決められるメリットがある
- 現状、課題があるのは確かだが今後ますます需要は高まっていく
- ケアマネージャーなどとコミュニケーションを密にし、ニーズを満たしたサービスを受けられるようにしよう
地域密着型サービスは、まだまだ利用者は少ないものの魅力の多い介護保険サービスです。
住み慣れた地域で生活を続けたいと考えている人は、ぜひ利用を検討しましょう。
こちらの記事を参考にして、ぜひ地域密着型サービスの利用を検討してみてください!
この記事は専門家に監修されています
介護支援専門員、介護福祉士
坂入郁子(さかいり いくこ)
株式会社学研ココファン品質管理本部マネジャー。介護支援専門員、介護福祉士。2011年学研ココファンに入社。ケアマネジャー、事業所長を経て東京、神奈川等複数のエリアでブロック長としてマネジメントに従事。2021年より現職。
監修した専門家の所属はこちら








